怪談レストラン③ 殺人レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集 松谷みよ子
絵 たかいよしかず
1996年8月10日 第1刷発行
株式会社童心社
怪談レストランシリーズ全50巻あるうちの第3巻目、殺人レストラン。
表紙にはナイフとフォークを振り上げる骸骨の姿が描かれている。カバーのそでには赤い蝶ネクタイを彼は付けた姿で描かれる。当レストランの案内人であるトウガラシのような顔の人間も蝶ネクタイをつけているところを見ると、二者は同一人物か。若しくは、このレストランで運悪く殺されてしまった人間の骨なのか。そこらへんの詳しい記述はない。
彼の名はコツコツガイコツ。
骸骨というものは、ホラー作品においてたくさん登場するが、骸骨自体に恐怖を感じないのは僕だけであろうか。それは、骸骨には物質感を強く表れていて、「死」からたくさんの時間が経過していることを示唆しているからではなかろうか。
唄うしゃれこうべなんて乙なものである。
ちなみに僕は学生時代、ほそっぴで顔は血色が悪かったので、「ホラーマン」や「死神」「チュパカブラ」などと言うニックネームで呼ばれていたときもあった(泣)
あらすじ
いらっしゃいませ…
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.2
舞台はドイツ、タロットカードの「塔」のような石造りのそれが、海を見下ろす小高い丘に建っていた。
壁面にはヒビがはいり、全三棟からなる塔はお客様という名の、獲物を待ちかまえている。そのレストランに入ったら最後、出ることは叶わないといういわくつきである。
ここにはかつて夫婦が住んでいて、塔を宿屋として使用し、宿泊業を経営していた。しかし、ある日訪れた客の豪華な荷物に目がくらみ、客を殺して荷物を奪ってしまう。それからというもの彼等は客を泊めては殺し、泊めては殺し…残虐な行為を繰り返し、この宿は殺人宿と化す。
そして幾年か幾日か、月日が経ち、この宿はいつのまにか殺人レストランになっていた。そのネーミングは、前身が殺人宿であることを考慮してのものなのかはわからない。読者はゲストとなり、当レストランでお料理(お話)をいただくのである。
作品は全15話のオムニバス形式で描かれ、内2話は殺人レストランに関する話、内13話は広義のホラーに関する話で構成されている。「殺人(血なまぐさい)」に関する話が多めの印象。誰も死なず、血生臭さもない話(春の日のふしぎ)も収録はされている。p22-23 レストランのメニューを模した目次が非常に面白い。
メニュー
最初のおはなし 殺人宿
天罰だわ。ああ、天罰がくだったのだわ
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.12
人間の欲望というのは怖いもので、金に目がくらんだ夫婦の目には実の息子すらも映らなかったということなのである。彼ら夫婦が息子を殺してから、どのような過程を経て、この殺人レストランがオープンしたかはわからないが、殺人が繰り返された場所が「殺人レストラン」という名前でレストランとしてオープンするのは当然の成り行きな気はする。住んでいた夫婦とオーナーの関係性は不明である。もしかしたら、夫婦が住むはるか前からこの塔では残虐な殺人が繰り返し行われていたのかもしれない。
写真のおはなし 白い手
だからいったではないですか…
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.21
お客が見たアルバムの写真に、自らの死に顔が写っている写真が挟まっているなんて、なんと恐ろしいことでしょうか。この後この客は写真通りに死んでしまうのだろうか。そういうモノをいけしゃあしゃあと客に見せる殺人レストランは容赦がない。きっとアルバムにはたくさんの人間の死にざまが記録され、殺人レストラン所有のコレクションとなっていくのであろう。
彼の運命がそういうものだったのか、「殺人レストラン」が彼の運命をそうさせたのかは、わからない。
おまえだ
ねぇねぇ、未来の結婚相手をしりたいとおもわない
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.24
学校の怪談においてとても有名な話。この手の話はいろんなところで見聞きしたことがある。
当時この話を聞いて、主人公が女の子であった為、僕は大丈夫だという謎の安心感をもっていたのが僕である。主人公が、ナイフを洗面器に落とした際、件の相手方はどんな儀式に興じていたのだろうか。相手方が主人公によって顔を傷つけられたことを認識しているということは、お互いが同じ時間に洗面器を覗いていて、女の子がナイフを落とすところを相手方が見ていたとでも言うのだろうか。また事件から20年の月日が流れていて、相手方が、大人になった女の子の顔を覚えているというのも不思議である。考えれば考えるほど、難しいが、おそらくこの作品が言いたいのは、「こんな晩」にも似た鬼気迫るラストシーンがすべてであろう。
とうげの一けん家
あのおじちゃんのせなかのとこに、顔じゅう血だらけのおねえちゃんがおんぶしてたの。
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.40
これもとても有名な話である。
おじいさんを主人公としたときに、人を殺した犯人が訪問してくる点と、殺した娘(の霊)が犯人におんぶをしている点が、後でわかるというのがミソである。例えば、友達の家に呼ばれて食事をして、その三日後、友達が殺人と死体遺棄の罪で逮捕されたとして、死体の隠し場所が自宅の押し入れで、食事をしたときにはすでに押し入れに仏さんがいたことがあとになって分かった場合、怖さが増幅するのと同じ仕組みである。要は「知らぬが仏」なのだ。
白いマフラー
ふふふ、ないしょのないしょ、ひみつよ。だれにもおしえない。
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.41
今までにないタイプのおしゃれな雰囲気が漂う作品。
沼のばあさまは着物を縫ってと言ったのに、なぜこの女の子はマフラーを編んでいるのだろうか。彼女は自らが着手する黒魔術に相当な自身があるようで、得意げにしているが、マフラーでも呪いの効力があるのかどうかは確認しておいた方が良いと思われる。もはやマフラーでは呪いの効力がないのは承知の上で、月夜の芳香に酔いしれているだけであろうか。
全ての行動を「月のうつくしい夜」に行うことがこの黒魔術のキーポイントであることは明白であるが、このことは術者の思いの強さを試すための要素に過ぎないと考えられる。それだけ人の想いと言うのは、大きな力を持っているという事なのだろう。
オオカミのひかる目
あしたも草原にいく。月もいいけど、オオカミのひかる目がみたい。
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.55
月よりもオオカミの目の輝きに魅せられた男の話である。危険なものにはどこか底知れぬ魅力があることを示唆しているのか。
刺繍布からオオカミが出てくる理屈については謎であるが、オオカミの魂を宿した布、とでもいうべきであろうか。使い方によってはお守りにもなり、自らを滅ぼすこともある、そんな布を寄越したおじさんの最期はどのようなものだったのだろうか。きっとこの村でオオカミは神聖な動物として祀られていたに違いない。
一本足のワルツ
じつはな、むかし、この学校はある貴族のお屋敷だったんだよ。
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.65
タイトル通りに一本足がワルツをするという話。
杉の木付近に一本の足が立っているというシーンを見て、小学六年生の時に僕の友達が夜中、自室のベッドで目を覚ましふと部屋の床を見ると、一本の右足があったというエピソードを思い出した。それは作中のような脚でなく、文字のごとく足であったそうだ。
杉の根元から発掘された骨が裸足の足一本、というのもかなり奇妙な話である。ほかの胴体や顔はどこにいったのだろうか。
おままごと
それから、となりの家はガランとしてすむ人がいない。
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.74
盲目の女の子には血だらけのおばあさんが見えていたのであろう。とても悲しい物語である。
母が一人でおままごとをする娘を発見した際、娘が耳なし芳一に見えたに違いない。怪異の間合いに入っている当事者のみ、幻覚が見えるパターンの作品である。
それにしても、なぜ不動産屋は殺したおばあさんの死体を庭に埋めたのか、土地を奪ったあとで最終的に売りに出すというのに、その行為には甚だ奇妙である。
真夜中の王女
ありがとう。おかげでたすかりました。さあ、おとうさまのところへもどりましょう
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.84
寝ずの番を任されたジュゼッペが、毎晩教会までの途次、老人からアドバイスを受け、その通りに行動し、悪魔の手から身を守るという話。
王女がいくら悪魔に憑りつかれていたとはいえ、人を食べた王女の身体はその後大丈夫なのだろうか。物語としてはハッピーエンドではあるが、少し違和感を感じる。ジュゼッペよそれでいいのかと彼を詰めたくなるが、中世ヨーロッパの暗澹たる時代においてはある種普通のことなのであろうか。
春の日のふしぎ
さえ子ーっ
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.91
珍しく血なまぐささがない話。
神隠しとはなんだろうか。山の神が子供をさらって、子供は返される場合もあるが、そうでない場合もある。そして前者の場合、当の本人は神隠しの記憶がなかったりする。今作においては神隠しの期間はおよそ丸一日であり、見つかった場所ははるか上流の家の大きさほどもある岩の上、本人の記憶の有無は記述されていないが、首のうしろのおできがなくなっていたそうだ。この最後のおできのくだりは、僕は神隠し関連の話で聞いたことはない。きっと山の神によく効く軟膏でも処方されたのだろうか。
おまえがくった!
手ぶらじゃ、家にかえれねえ
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.99
この話で興味深いのは、太ももの肉を切った男に対しては何のお咎めもなしなのに対し、それを喰った妻だけ制裁を受けるという点である。
作中を通して、男は信心深く、女は下品、乱暴に描かれる。これは正直おじいさんが得をし、いじわるおばあさんがひどい目をみるという日本の昔話に近いものを感じる。やはりいつも謙虚でいようと思った。
彼女はいったい、どこへ連れていかれたのだろうか…
池のふちの道
たすけて、たすけて
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.108
人生において人を二回見殺しにしてしまう男の話。
二回目は死者は実子であるということもあって男の悲しみはかなりのものだったと想像できるが、このことは一回目に見殺しにした男の怨念であるとは考えにくい。しかし、結果的に、一回目の見殺しがなければ、二回目の見殺しの際は池に戻っていたはずなので、全ては因果応報なのである。
三度殺された死体
そ、そうですね。おりてしまったんですよ
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.118
これは笑い話ととってよいのか、どうなのか。落語のようなオチがあって、タイトルもおしゃれである。
死んだ父をそのまま持ち帰ろうとする兄弟の行動そのものは恐怖である。そして、自分が殺してしまったのかと思って、父を車窓から放り投げた男の行動もなかなかクレイジーである。食堂車からもどった兄弟は、父が息を吹き返したと喜んだりしたのだろうか。
おばあちゃんの殺人レストラン
おばあちゃん、にっこりわらうんだ。
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.122
夜でしょう、まっくらな庭で、おばあちゃん、カイチューデントーもって、それが下から顔をてらしたりすると、おにばばみたいだったよ。
思えば、うちの実家の庭にもたくさんナメクジがでた。
そのたびに祖母がお皿にビールを注ぎ、一晩おいて、ナメクジを大量に処していた。そして朝になると、白っぽくなってビールを吸い込み膨れたナメクジの骸がビール溜まりにぷかぷか浮いているのである。今の時代、優れた殺虫剤が出回ってるおかげでこのような原始的な殺戮シーンを見る子供たちは少なくなったのではなかろうか。
良くも悪くもうちの祖母も「おばあちゃんの殺人レストラン」のシェフだったわけである。
最後のおはなし リプレイ
「リプレイ」「バキッ!」「リプレイ」
怪談レストラン編集委員会 [1996] 『殺人レストラン(怪談レストラン)』 p.135
この話はアニメ版怪談レストランでもやっていたのを鮮明に覚えている。
実際のゲームをプレイしたとき、回復アイテムや武器の弾薬がない状態で、セーブをしてしまって、何度もゲームオーバーになってリプレイしたものの、同じ状態で同じセーブポイントからしか復帰できなくなり、所謂「詰み」の状態になったのを思い出した。その時は泣く泣くゲームのセーブデータをリセットし、「最初から」にして解決したが、これが現実の問題である場合、リセットはそれすなわち「死」を意味するのであろう。
まとめ
殺人レストランに出てくる料理はどんな風であるべきなのだろうか。
人を殺すシーンに重きを置き、振り落とされる鉈、裂ける肉、ほとばしる血液、断末魔を描く場合、これは所謂スプラッターであり、広義のホラーに分類されるものの、これだけを描いていては殺人レストランの料理とは言えないのではないか。
では、殺人の犯人を推理し、殺人の仕組みを解明していくストーリーはどうだろうか、これでは言わずもがな探偵小説になってしまう。そしてスプラッター要素と、推理要素を良い感じで合わさるとそれはサスペンスになったりする。そして、このサスペンスに怪異(超自然的な何か)が合わさることによってはじめて殺人レストランで提供される料理になり得る。1
多少暴論、というか定義が曖昧な気はするが、「殺人」というモチーフの怖い話と言うのは当然「人が死ぬ」こと、「血生臭さ」は避けて通れない。もしくは人を殺そうとしたり、呪ったりするマイナスの感情が必要である。ただし、それだけでは駄目なのである。そこに所謂お化け要素、因果応報を説く説話的要素等が入ることによって、はじめて、「怖い話」となるのではなかろうか。そこらへんの加減がとても難しいものである。
最後に、この本の表紙を飾る骸骨は、支配人と同一ではないと考える。それはこの塔において長い間、たくさんの人間が惨憺たる最期を遂げてきた歴史と深い関係がある。その血生臭い歴史の中で「殺人レストラン」とは一過性のものに過ぎないということである。今までも「殺人宿」など、様々な矯飾をもってこの塔は人の血を飲み込んできた。将来この塔は「殺人レストラン」でなくなるかもしれない。しかしこの塔が延々と殺人を繰り返し人の生き血を吸い続けるということは変わらないであろう。オーナーが誰であろうとこの悲劇は永遠に続くのである。その事を示唆するために、被害者である方の「骸骨」を表紙にしたのだろう。もしくは「塔」を表紙にしてもよかったのかもしれない。
そんなすっ頓狂な考察を述べて、この稿を閉じたいと思う。
- 探偵要素がなく、スプラッター+怪異でも殺人レストランで提供する料理になり得る。 ↩︎
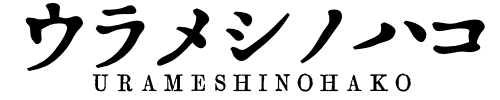


コメント