うずまき
伊藤潤二
2010年9月4日 初版第1刷発行
小学館(BIG COMICS SPECIAL)
ホラーとは何か、その問いに対する回答として、お化けが登場するジャンルであると考える方はきっと多いはずである。かつて昭和と呼ばれた時代、どこそこの踏切で、哀しい轢死事件があり、その被害者が令和に至った今日においても夜な夜な幽霊となって現れて、新たな犠牲者を踏切に招き入れる、といった話を想起せずにはいられないであろう。そしてそれが他殺によるものか、自殺によるものかで、幽霊によるターゲットの選出に明白な共通点があったりなかったりするのである。僕もそんなホラーは大好物ではあるものの、今回記述すること伊藤潤二作品においては、ホラー漫画であることは間違いないのだが、彼の作品にはあまり幽霊が登場しない。1
では何をもって彼の漫画がホラー漫画たり得るかというと、それは突飛なストーリーの中で展開される猟奇的でり、奇妙、神怪であり、甘美な描写によるものであろうか。
美しいキャラと悍ましい怪異が織りなす作品の数々に僕は魅了された。初めて手に取った彼の漫画はたしか『怪奇カンヅメ』であったと記憶している。当時高校生くらいで、色々なホラー漫画や怪奇小説を読み漁っていた時分である。中でも強烈だったのは「なめくじ少女」と「隣の窓」である。なめくじ少女のグロテスクさの中に存在するエロティック、隣の窓に登場するお隣さんの禍々しさには当時、すごいホラー漫画を見つけてしまったと歓喜したものだ。
そして、今回は『うずまき』について書評を書こうと思う。『うずまき』に出会ったのはもう少し後の話で、書影の小学館が出版している分厚い漫画が初見だった気がする。この作品は伊藤潤二が青年漫画雑誌2へ掲載された初めての中長編連載漫画であり、うずまきに魅せられ、侵され、一体化した、ある文明の話である。
あらすじ
私の生まれ育った黒渦町・・・
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.3-5
これからお話するのは・・・・・・
この町で起こった奇妙な話の数々です。
五島桐絵は黒渦町の黒渦高校に通う女子高生である。
同じ町内に暮らし、同じ高校に通うその彼氏斎藤秀一の父が「うずまき」に心酔した果に、桶の中で身体をぐるぐると渦巻き模様に捻じり自殺したのを皮切りに、渦巻きに関する怪異が彼らを襲う。
書評
「うずまき」とは何か
物語のある種のテーマである「うずまき」とは何であろうか。それは外側から内側、若しくは内側から外側に向かって旋回している曲線であると言える。前者であれば力の集約や鋭利な円錐状の物体、収束、後者であれば、力の解放、際限のない風景、拡散といった両義的な概念を想像する。作品のタイトルを敢えて平仮名で表記している事も考慮すると、無論伊藤潤二が描きたいのは「うずまき」そのモノでなく、渦巻きのメタファーであることは言わずもがなである。物語に出てくる「うずまき」の解釈に重きを置いて記述し、書評とする。
うずまきマニア
そして書斎にあふれ返ったうずまきを一日中眺めているんだ。
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.22
うずまき愛好家の秀一の父と、うずまき恐怖症の秀一の母という相反する要素が描かれている。これは愛好や恐怖といった客体に向けられる感情は、状況次第で良くも悪くも結果が180度異なってしまうということを表している。「可愛さ余って憎さが百倍」と言うことわざにもある通り、重要なのは好き、嫌いという要素ではなく、その度合いなのである。3また、ひとたび渦巻きの曲線の向きが反転すると形も意味合いも反転してしまうことが暗示されている。
傷跡
桐絵さん…
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.99
何だか変な感じ…
右目が変なの…
視点が定まらなくて…
幼少期にけがをして額についた傷がきっかけで好きな男の子と仲良くなることができた桐絵の同級生の黒谷あずみは、以降その傷の不思議な力によって艶福たる人生を送ってきた。
やがてその傷は渦巻き模様に変化し、顔中に広がって、自身の眼球をぐるぐると飲み込み挙句の果てには自身をも飲み込んで、彼女は消えてしまう。
人を引き付ける魅力というのは、あまりに強いと、自身の身も亡ぼすということなのであろうか。僕が中学生くらいの時、バレンタインデーになると複数の女の子からチョコレートをもらう同級生がいた。彼は一気にそのチョコを食べ、後日虫歯になったエピソードを思い出した。
窯変
やきものというのは、土と炎の芸術…
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.117
いうなれば大自然の神が作りあげるといってもいい…
人知の及ばぬ世界だ…
時として我々の計り知れぬ結果が出ても、不思議はないんじゃないのかな?
桐絵の父がトンボ池4から土を採ってきて自宅の窯で陶芸品をつくる話。
それはまるでヨーグルトづくりに似ているではないか。牛乳とヨーグルトの種菌を混ぜるとヨーグルトができる。そしてその、ヨーグルトの一部を牛乳に混ぜるとまたヨーグルトができる。つまるところ、「うずまき」を通して、一度汚染された物体や土地は、根本的な原因を取り除かない限り、除染は不可能であり、それを媒介することで「うずまき」が広がっていくことを示唆している。
ねじれた人々
お父さん…
もうやめて…
私たちはもう二度と離れない。そうだ…
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.170
永遠に……
渦巻きの曲線を目で追っていると、なんとも歯がゆく感じる。それは目的地を渦巻きの中心として、外側から内側へ向かう場合、曲線を無視してまっすぐ中心に向かえば最短で到着することができるのにもかかわらず、ぐるぐると何回も旋回しているその様は、遠回りにほかならないからだ。
この事は人の言動の捉え方とその諸相に類似する点がある。陰鬱な状況に長い間身を置くと、人は自分の言動や他人の言動の受け止め方を間違えてしまうものである。それは人の善意を悪意と捉えたり、人の不幸を幸と感じたりすることであり、作中ではこの事を「ねじれる」と表現している。そんな捻じれた2つの家族の間にそれぞれ生まれた男女は、このいがみ合う人間達とは対照的に愛し合った。やがて2つの身体を蛇の交尾の様に絡み合わせ、海へ消えていく何とも哀しく美しい物語である。捻じれた果てに、彼らは彼らの幸せを見つけたのであろう。
悍ましいことには変わりはないのだが。
巻髪
五島さん!!
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.191
いい加減に負けを認めなさいよ!!
目立つのはどちらか一方で十分なのよ!!
「うずまき」が一度人間の頭部に宿れば、カールアイロンで施した様なくるくるの髪型になり、それは魅力を放ち出す。その魅力は様々な人を魅了するが、やがては「うずまき」は宿主を喰い殺してしまう。桐絵と関野の髪の毛バトルは見物である。
びっくり箱
俺の愛で車を止めてやる!!
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.212
渦巻きの旋回する模様は、どこか諧謔的である。この話は、そんな渦巻きの側面を描いている。クラスのお調子者が桐絵の気を引こうと行った馬鹿なアプローチの過程で交通事故に遭い、凄惨な最期を遂げる。車のホイールアーチに渦巻きの様にぐるぐると巻かれ死に至った彼は、ぐちゃぐちゃになった身体を縫合された後で埋葬されるが、事故時体内に残された車から外れた巨大なバネのパーツを脚の様に巧みに使い、ぴょんぴょんと跳ね回るという妙技を披露している。ギャグとホラーの組み合わせが、絶妙な旨味を引き出している。
ヒトマイマイ
見ろ…やつが
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.250
這い回った跡だ…
僕は子供の頃、自分の腕にカタツムリを這わせてよく遊んでいた。絶妙な吸着力と粘液のヌルヌル感がたまらなく好きだった。今考えるとよくそんな事をしていたと驚愕する。子供の好奇心とは怖いものである。この話では「うずまき」は醜さを表現しているのだろう。渦巻き模様からカタツムリの殻を連想してヒトマイマイなる生物を生み出した伊藤潤二のセンスには脱帽である。このヒトマイマイになってしまった片山は普段から動きが鈍く、クラスメイトから馬鹿にされていた。彼は最初から最後まで可哀想な奴であった。こう言った伊藤潤二作品の、本当に救いのない所も、僕はとても好きである。
ちなみに、ほとんどのカタツムリの殻の渦巻き模様は、右巻きなのだそうだ。
黒い灯台
でも、どうしてこんなふうになってるのかしら?
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.290
そういえばこの部屋全体も何となく熱で歪んでる感じ…
虫眼鏡の凸レンズを通って一点に集められた太陽光というのは、収れん火災を引き起こす可能性があるが、この話には渦巻きのレンズによってめちゃくちゃに反射された太陽光が人体を真っ黒に焼き尽くすという事象が描かれている。光を一点に収束させることによってエネルギーを発生させるのであるから、光の乱反射は普通、物体を黒こげにするほどのエネルギーをもっていないはずである。この場合の渦巻きはその中心から外側へ無制限に続く回転曲線によって太陽光の熱量を無限に拡散させるという役割を果たしているのかもしれない。
蚊柱-臍帯
ホホホ無駄よ…
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.326
開けなさい!
この手の蚊やコバエの鬱陶しさは天下一品で、どこからか家に侵入し、吸血したり、卵を産みつけたり、非常に嫌なものである。先日もいつのまにか僕の部屋にノミバエが現れて、顔の前をブンブン飛び回るのである。まるでかまってちゃんのように、僕の手の甲にとまり小刻みなステップを踏むのである。あれはもうこちらをおちょくっているとしか言いようがない。
黒渦病院に入院している妊婦たちが、夜な夜な蚊の様に、別の入院患者の血を吸う奇妙な物語。直接うずまきが影響して妊婦たちがおかしくなる描写はないが、しつこく旋回し、人間の血を求める蚊が、渦巻きのメタファーとして描かれている。彼女たちがドリルの様な器具を使って人の頸に穴を開けるその様は狂気そのものである。誕生した胎児の胎盤は切っても切っても成長が止まらずやがて渦巻き模様のキノコの様な胎盤を形成することから、胎児に胎内回帰願望があると考え、外科手術によって胎児を母体に戻る手術をする医者の描写は圧巻である。
伊藤潤二らしい、とても怖い作品である。
台風1号
まったくお前はすごい女だぜ。
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.387
台風1号を恋に狂わせるとはな!!
渦巻きといったらやはり台風は外せないであろう。ところで、台風1号というのは年が変わって以降北西太平洋で一番最初に発生した台風を1号とし、それ以降発生した順番に番号をつけていくらしい。5
本作での時季は不明だが、今年にはいって一発目の台風だったようだ。最後に台風2号が発生したことが描かれていて、次の話である「鬼のいる長屋」で黒渦町に直撃している。この事から世界の台風はすべて黒渦町にやってくることを示唆していると言える。黒渦町の地下に眠る「うずまき」遺跡が台風を誘引しているのであろうか。そして、なぜか台風1号は桐絵を狙っており、その理由は不明である。
鬼のいる長屋
…それにしても…
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.416
うおの目が痛むな…
魚の目というのは芯の部分を除去すると、その分がごっそりへこむイメージがあったが、本作では、逆に患部が突起した渦巻き模様型にせり出してくるのである。やがて全身に魚の目ができて死に至る。登場人物である若林もたまたまこの長屋に住んでいたことから、この病気に罹患し、体中から魚の目が生えて鬼のような見た目になる。その後明らかに性格が狂暴化することから、渦巻きをせり出させることで想起される円錐の鋭さ、凶器のようなものを表現していると言える。
蝶
あのガキ共、手がつけられないんだ。
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.453
この当たりから黒渦町はだいぶ雰囲気を変え、まるでディストピアのような様相を呈する。日頃のうっ憤を晴らす為、子供たちまでも、渦巻きの風を起こし、町を破壊するのである。この話は長かったうずまきの物語を終局へと向かわせるスイッチ的な役割を果たしている。
混沌-遺跡
…私も、もう力は残っていないわ…
伊藤潤二 [2010] 『うずまき』 p.607
あなたとここに残る…
黒渦町は地上にトンボ池を中心として、残った長屋を渦巻きのように再建築することで巨大な渦巻き都市を作り上げる。そして池の水が消失したトンボ池は、地下深く螺旋状の階段を形成し、うずまき遺跡へ桐絵と秀一を誘うのである。遺跡には黒渦町の人たちが渦巻きのように絡み合い死屍累々を成していた。二人はやがて絡み合い、黒渦町と、かつてこの町に住んでいた人々と、遺跡と共に、深い眠りにつく。
ここで地上の巨大な渦巻き型に建築された長屋と、地下の渦巻き遺跡、渦巻きのようにねじれた人々。そして地上と地下上下の渦巻きを繋ぐ螺旋階段の空間に、下から突き上げる渦巻きの塔がガチっと噛合うことで、「うずまき」は収束し、物語は終局を迎えるのである。
まとめ
『うずまき』という連載作品における恐怖の概念として「渦巻き」を選んだ伊藤潤二はとてもすごい。この作品群には、渦巻きのメタファーとしての恐怖が盛り沢山である。渦巻きをここまで深堀りして作品に落とし込むことはもはや尋常ではない。僕は日常生活で渦巻き模様を見るたびに、『うずまき』が脳裏をよぎるようになってしまった(喜)。
本稿の最初で作品『うずまき』を「うずまきに魅せられ、侵され、一体化した、ある文明の話である」と表現した理由については種々あるが、一番肝心ものとして、物語の最後で描かれる、黒渦町の地下に存在した遺跡に屹立するうずまきの建造物を挙げる。ことの発端はこの建造物(及びそれらが成す遺跡)にあり、それは黒渦町が誕生するもっともっと前から地下に存在し、一定の周期をもって(遺跡真上の)地上に形成された文明を取り込み破壊してきた。誰が何の為に遺跡をつくったのか、なぜ地上の文明を吸収するのか、いずれも仔細は判然としないが、『うずまき』は、うずまきに魅せられ、侵され、一体化した、ある文明の話である。
あなたにとっての「うずまき」は、何ですか?
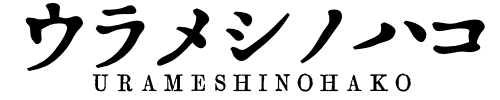


コメント