黒い家
貴志祐介
1998年12月10日 初版発行1
角川書店(角川ホラー文庫)
この物語にお化けは登場しない。
ただし、やけにでかい包丁を振り回す女が登場する。
それが、猛烈に怖い。
きっと彼女の持つそれが例えば「人参」であったとしても、その諧謔的な要素が恐怖を増大させるに違いない。
貴志祐介作品で初めて読んだのが今作である。あまりにもリアルに描かれる保険会社でのシーンは彼の生命保険会社勤務時代の経験から想起されたものであろうか。保険契約を締結した双方の生々しいやりとりや「潰し屋」と呼ばれる人たちの事、生命保険を査定する側の葛藤等が、ありありと書かれている。
人間の心の闇を心理学的アプローチで探求している点も面白い。
第4回日本ホラー小説大賞大賞受賞作品。
あらすじ
この人間には、心がない!
貴志祐介 [1998] 『黒い家』 p263
若槻慎二は昭和生命京都支社に主任として勤めている。業務の一つである生命保険の査定をめぐり、彼は様々な人間模様を知っていく。
彼は生命保険加入者である菰田重徳の急な呼び出しで菰田家に訪れた際、菰田の一人息子である和也の縊死体を目撃することになる。息子の骸を前にしたときの菰田の空空しい態度が気になった若槻は、菰田重徳について独自に調査を始める。その先に悍ましい結末が待っているとも知らずに…
書評
居心地の悪い家
立派な生け垣のある家を過ぎると、その向こうに、半ば朽ちかけたような真っ黒な家が見えた。
貴志祐介 [1998] 『黒い家』 p80
若槻が訪れた黒い家、ひどい悪臭が漂い、廊下は黒光りしていて、庭にはおびただしい数の犬がいる。それら一つ一つの要素が、動物的で猟奇的な妄想を掻き立て、生理的嫌悪を催す。初訪問で彼は、子供の縊死体を発見してしまうが、その時にはすでに家の風呂場では殺戮の限りが繰り広げられていたと考えると、非常に怖い。
廊下と縁側に挟まれ、襖で隔てたれた連続した十畳ほどの和室で、南向きの縁側から室内に暖かい光が差し込む。日本庭園を通った風は、椿の彫刻が施された欄間から室内に太陽の香りを運び入れる。お盆に載せられたガラスのコップにはキンキンに冷えた麦茶が注がれており、その外側を結露の水滴が伝う。こんな家を「居心地のいい家」と呼ぶのであろう。では何をもって「居心地が悪い家」というのであろうか。見た目の悪さや悪臭などの要素はもちろん気持ちの良いものではないが、本当の意味で重要な要素と言うのは「悪意」の有無ではなかろうか。
「黒い家」は「悪意」で満ちている。それは、自らの欲望を満たすために、被保険者や自分たちの邪魔をするものを平気で家に招き入れ、殺害してきた。その死体は台所に穴を掘って捨てた。そして、次なる死体をいつでも放り込めるように穴は塞いでいない。このような果なき悪意が真っ黒な渦となって、家を覆っている。
性善説と性悪説
善意で踏み固められた道も、地獄へ通じていることがある…
貴志祐介 [1998] 『黒い家』 p200
かつて孟子と荀子が唱えた性善説、性悪説とはどのようなものであろうか。
両論はそれぞれ人間の本質(性)を「善」と捉えるか「悪」と捉えるかを端緒とするが、その骨子は「教育(環境)の重要さ」と説いたものであるそうだ。つまり、ボランティアをする人が増えているので、性善説も一理あるな、とか、犯罪者に対して、人間は性悪説によると皆「悪」だから仕方ない、などと言った意見における性善説や性悪説の解釈や意味は根本的に間違っているということだ。要は人は「善」でスタートするが、きちんと教育をしないと「悪」になると説いた孟子に対して、荀子は人は「悪」でスタートするのだから教育が必要であると反論した形になる。しかしその差異は「教育の必要性」の論拠の違いであり、両論は本質的な部分で似通っている。
以上を踏まえ、物語に登場するキャラクターの標榜する思想を記述する。
若槻の場合
人間の性は「悪」であるとする立場。
若槻は仕事柄、たくさんの人間を目にする。その中には、作中に登場する人を騙す気満々の中小企業の社長とチンピラのようなどうしようもない人間も含まれる。そういった人間達の煩わしさから、彼等を「異常」とラベリングし、菰田一家もそうであるという解釈を行った。また、その行動規範の根本には、彼が小学生の時に自殺した兄の存在も大きいだろう。兄が自殺したのは自分の責任だ、とずっと負い目を感じていた彼は、自分自身を「悪」とラベリングすることで、少しでも気が楽になったのではなかろうか。
恵の場合
人間の性は「善」であるとする立場。
恵の両親は彼女にラベリングをした。かわいい恵という人形が自分たちの思い通りに生きるように、彼女を縛った。それは所謂健常者が犯罪者をラベリングして罵り、冷酷に排他することとある種同義であった。彼女はそういった線引きをしてしまうこと自体が問題であり、どんなに異常な人間であっても、性が「悪」なのではなく、環境やトラウマが彼等をそうさせてしまったと考えるべきであると主張する。
物語の最後で若槻と彼女が思想の和解をしているが、その二人の決意はこれから訪れる嵐の前兆である。
人が人と分かり合う日は来るのだろうか。
金石の場合
人間の性は「悪」であるとする立場
金石がどのようにこのような思想に至ったかは不明であるが、ロンブローゾの生来性犯罪者説から転じて、サイコパスという存在の肯定、その存在が近年増えていると予想している。若槻と金石がスナックで話すシーンにて、彼は若槻に対し菰田重徳は危険と警告するも、黒幕は菰田幸子である点を見落としている。それは人を外形で判断してしまった彼の落ち度であり、そのせいで彼は幸子に地獄の様な拷問をされてしまう。こと心理学を専攻する彼がこのようなミスリードをしたことはとても皮肉なことである。そして、彼の思想と彼がホモセクシャルであることは何等かの関係性があると思えてならない。
菰田幸子の狂気
結論から言うと、あの作文に書かれている夢は、やっぱり異常だったわ
貴志祐介 [1998] 『黒い家』 p262
リングにおける怪異が「貞子」であり、呪怨における怪異が「伽椰子」であるように、黒い家における怪異は「菰田幸子」である。しかし、「貞子」「伽椰子」と「菰田幸子」には決定的な違いがある。それは言わずもがな、前者は死んでいるのに対し、後者は生きているということである。死者が恨みをもって世の中に具現化し、超自然的な何かによって生きている人間に害をなすというのは、ある種ホラーの世界では日常茶飯事である。それに対し「菰田幸子」は生きているにもかかわらず、物理的な脅威をもって人間に害をなす。「生きているにもかかわらず」と記述したが、本来の我々の生活における第三者による害おいてその根本原因は「生きている」人間によるものがほとんどである為、当たり前ではあるが、改めて本当に怖いのは人間である、という言葉を改めて反芻した。
菰田幸子は異常である。それは若槻の7階自宅を襲撃した際、若槻と7階でばったり会わないように細心の注意をはらい、エレベーターで5階までのぼり、そこから7階までは階段で向かった点や、潰し屋としてのプロである三善を毒牙にかけた点、自らの欲望を満たすために人を殺すのをまったく厭わない点、気配の消し方など、枚挙にいとまがない。もはや普通のおばちゃんでないことは明白である。
恵の説を踏襲するなら、そもそも彼女の心はいつからなくなったのであろうか、という疑問が残る。彼女をここまで異常たら占めたものは何だったのだろうか。彼女が小学校5年生で「ブランコの夢」を書いた時にはすでに心はなくなっていたのであろう。幼い彼女が経験した精神的外傷の詳細は描かれてないが、考えただけでも哀しく、恐ろしい。
まとめ
「菰田幸子」というモンスターを観察対象として、その狂気の発端を先天的なものか後天的なものかという理由付けに重きをおいたとて、その如何によって「菰田幸子」のようなモンスターへの対処法は変わらない。物語の最後で若槻が想起した芋虫のくだりは、結局、先天的なものであるとラベリングし、狂気の対象を排他しても、実際にそれが害意をもって牙を見せてきた時、我々はその獣に向き合い、戦わざるを得ないことに彼自身が気づき、そう決心したことを示唆しているのであろう。
それにしても「菰田幸子」の物語後半の狂気っぷりはとても怖かった…
やっぱり「包丁」怖い…
映画も…みてみよっかな…
- 初出は角川書店より「黒い家」1997年6月30日 初版発行 ↩︎
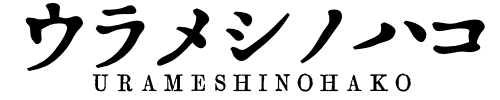
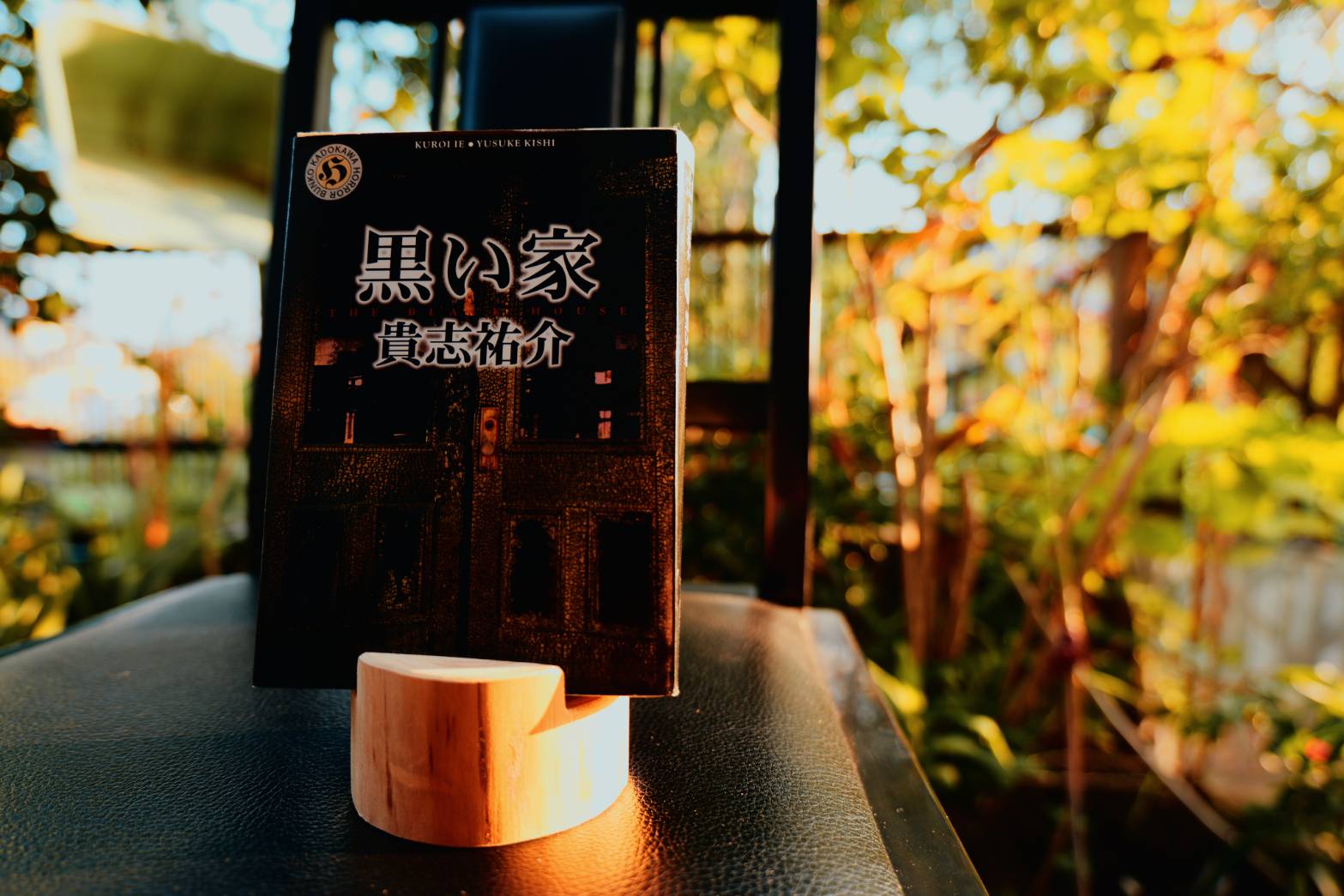

コメント