独白するユニバーサル横メルカトル
平山夢明
2009年1月20日1 初版1刷発行
光文社(光文社文庫)
この本に出会って平山夢明を知った。
表紙とタイトルに惹かれて購入したわけであるが、「ユニバーサル横メルカトル」が何なのかまったくわからず、読んで地図のことであると知って驚いた。表題作以外の作品も中々の粒揃いでどれも素敵だ。人間の悪意を生々しく描く筆致は血なまぐさい想像を掻き立てる。
暴力、カニバリズム、虐待、殺人、拷問などをテーマに描かれた作品群は、目も当てられない惨状を展開している。しかしその中に、風刺的要素や美しさ、諧謔的要素や人間の普遍性などが描かれていて、グロテスクが苦手な僕だったが、夢中で読んだのを覚えている。
表題作の「独白するユニバーサル横メルカトル」はこの作品群の中では残酷描写が少なく、割と誰でも楽しく読める内容となっているのでおすすめである。(人の皮で作った地図が登場するが。。。笑)
表題作は「このミステリーがすごい!」2007年度国内部門第1位受賞作品。
書評
C10H14N2(ニコチン)と少年-乞食と老婆
じじい!俺の話を黙って聞け!
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.36
一番好きな作品。作品を読みおわったあとに、タイトルであるニコチンの意味が分かり笑った。ニコチンというのは脳の快楽物質を放出させることから、「暴力」には悦楽をもたらす成分が含まれていることの示唆か。この町は「暴力」で横溢し、たろうを殴った少年、おじいさんを殴ったパン屋のおやじや警察官、そして最終的にたろうまでもが暴力に訴える。その残酷な空気は次々と人に感染し増々暴力を助長させる。ニコチンの理由についても暴力的で救いようがない。
それにしてもこの作品の副題、なぜ乞食と「老婆」なのだろうか?老婆なんてでてきたかしらん。
Ωの聖餐
ようこそ……我が宮殿へ
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.53
この作品は単なるスプラッターカニバリズム作品ではない。脳を食べることで記憶が継承する点はΩの特異な体質が成せる技と言え、神々しさすら感じる。主人公がΩを食べたことにより、それはまさに聖餐となるわけである。そんなΩにしても数学の真理を解明できなかったことを鑑みると、数学にもまた別の宇宙があらことを示唆している。ひとまず、絵的な気持ち悪さと作品のテーマに乖離があり過ぎて、逆に凄惨なΩの部屋にすら、どこか美しさを感じずにはいられない。まさにそこはΩの宮殿なのである。
無垢の祈り
私を読んだのは君かね
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.116
「救い」を描いた作品だと考える。
少女が試みた連続殺人犯へのコンタクトは幸か不幸か成功し、ラストを血みどろに染めるが、そのシーンがとても気持ちの良いものと感じたのは僕だけではないはずである。周知の事実であるが、急迫不正の侵害に対して法律はなんの役にも立たない。刑法の条文を読み上げその行為が犯罪の構成要件に該当することを示し、民事上の訴訟もついでに提起することを標榜したところで、振り上げられた凶器を止めることはできない。少女にとって連続殺人犯の登場は「救い」になったに違いない。この後に少女自身が彼に臓物を引き摺り出される可能性があることも含めて。
オペラントの肖像
ルーベンスか
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.123
180の分野における条件付けは人類に何をもたらすのだろうか。猿破壊実験を想起するオペラントはその部分強化を要として発展してきたが、ひとたび堕落者の烙印が押されると矯正所なる地下要塞に幽閉され、自らが猿となりレバーを下げ続ける点は皮肉を感じる。
条件付けが難しい分野として芸術が挙げられる点も面白い。人間の深層心理や経験、恣意的な事柄等が偶発的に混ざり合い成されるアートは確かに条件付けには適さないであろう。そして、堕落者が隠れて宗教画のペンダントを飲み込む描写は粋なものである。彼らは、その不確実性をその身に宿すことで、暗澹たる世界に一途の光を見出していたのである。
卵男
ああ……厭だ。厭だよぉ
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.157
所謂叙述トリックが使われている作品。本来の更正という刑罰の目的の範疇を超える死刑という判決を受けた囚人に対して、その精神の正常、異常の結果によって、死刑の執行が世論から批判されてしまう世界というのは、どうなのだろうか。「死刑」の是非について語らずに、一部のよくわからない批判家を黙らせるために、汎用人型ロボットを作り上げた人類は本当に身勝手な生き物である。
卵男作戦はそのような意味で今の世界を揶揄しているように思えてならない。
すまじき熱帯
生ハメ半ハメ赤ハメ!
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.203
ジャングルの奥地、そこは人の命が軽く扱われる世界であった。彼等が作業の途中、あるゲームをして勝った人間をその場で殺すという遊びをしていたのが強烈に印象に残った。なぜなら彼らは「死」を罰として扱っていないからである。死んだらその人は二度と元に戻らないという当たり前のことが欠落している。というよりもその事の善悪の基準がないといったほうが良いだろうか。きっと彼等には「個」の概念がなく、皆で一つという共通認識のようなものを持ち合わせているのであろう。この作品を読んで、極論ではあるが、文化の違いを尊重し理解し合うのことの難しさを感じた。
独白するユニバーサル横メルカトル
私は建設省国土地理院院長承認下、同院発行のユニバーサル横メルカトル図法による地形図延べ百九十七枚によって編纂されました一介の市街道路地図帖でございます。
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.225
平然と地図が独白を始める。古今東西このような話を聞いたことがない。はるか昔より、人と地図はその絆を深めてきたと言える。それは世界地図が登場する以前、人は自らの生活圏における狭い世界の地形を記録するだけではなく、ちょっとした伝聞的要素を伴ったメモ書きなどをしてきたことからも明らかである。地図にはその持ち主ごとに異なる独自性があり、持ち主との間主観的な世界を構築している。
そして、本作ではその地図にスポットがあたり彼は悠々としゃべりだすわけである。主人の残忍性や、その息子の狂気性が薄れるほどのインパクトがあった。
怪物のような顔の女と溶けた時計のような頭の男
いぎぎぎぎぎぎぎ
平山夢明 [2009] 『独白するユニバーサル横メルカトル p.294
拷問する者とそれを受け者、両者の境遇が奇妙に交差する。物語のラスト、拷問者という職を降りたMCを処分しに手先が間も無くやって来るというのに、ココが夢に現れるのをのんびり待つという記述は、彼の恋心を想起させる。作中を通してグロテスクであるのに対し、どこか切なさが残る。
まとめ
血を見るのが苦手な僕にとってこの作品群は中々の強敵で、ぷるぷると震えながら読んだ。そもそも、こういった「気持ち悪いもの」を見ようと思ってしまうのはなぜなのだろうか。人間の歴史の中におけるコロッセオでの殺し合いや公開処刑などがその理由に近いのではなかろうか。全員がそうとはいわないが、そのようなイベントに大衆が集まって見物していたという事実がある以上否定はできない。まぁそれを楽しんでいたかどうかはよくわからないが。
そして時代は変わった。現代において、目に見える表面的な部分はホワイト化され、きれいに、きたなくないように、変化している。しかしその洗浄作業をすればするほど、居場所をなくした人間の闇は反対に真黒く、より対照的に、我々の心に黒を落とすのではなかろうか。当然、その是非や真偽についてはここで僕が論ずるつもりは毛頭ない。
- 初出は光文社より「独白するユニバーサル横メルカトル 平山夢明短編集」2006年8月25日 初版1刷発行 ↩︎
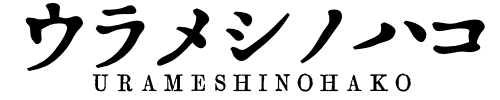
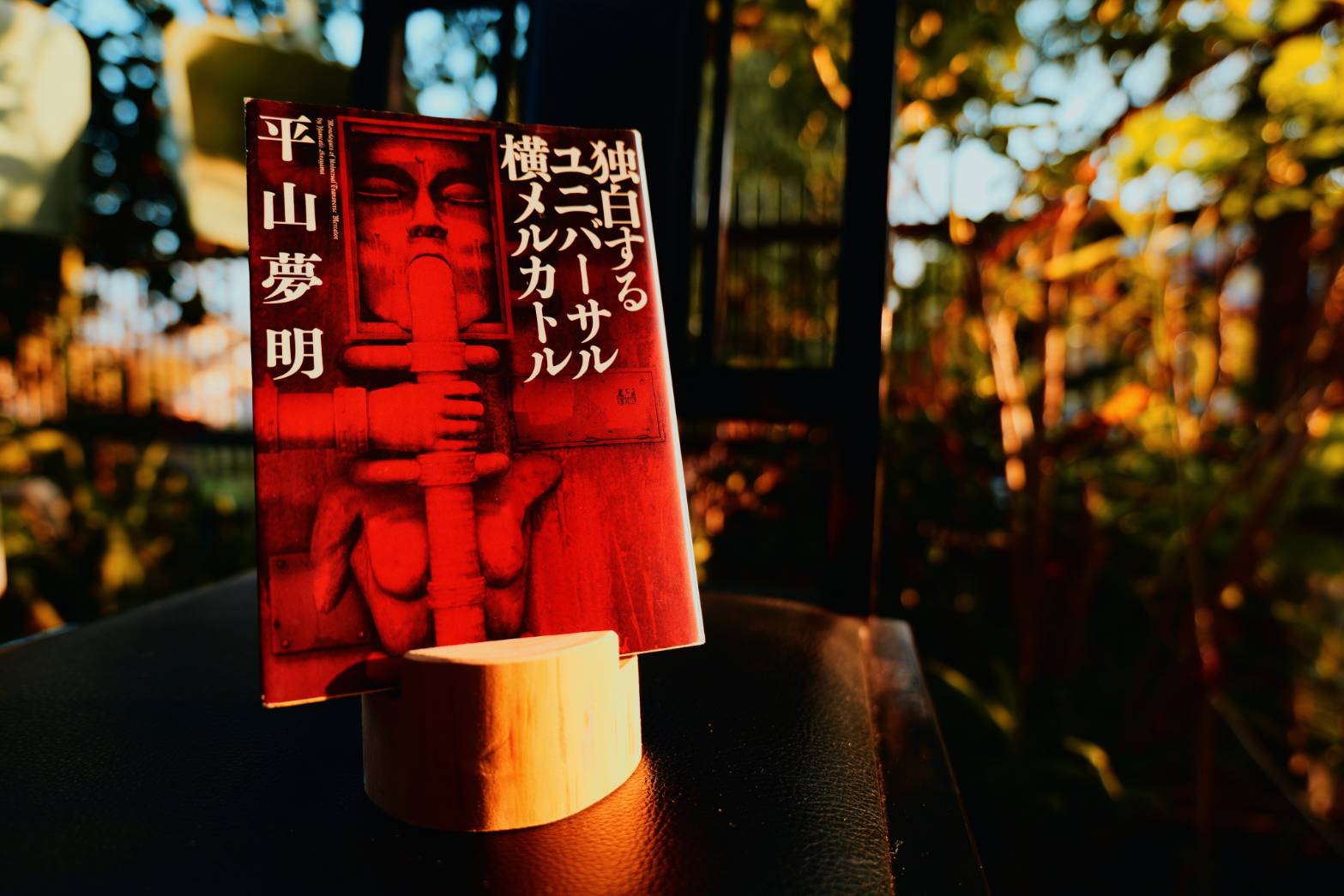

コメント