恐怖新聞(全5巻)
つのだじろう
1巻 1996年12月10日 初版発行1
2巻 1997年2月10日 初版発行
3巻 1997年3月31日 初版発行
4巻 1997年6月10日 初版発行
5巻 1997年8月10日 初版発行
秋田書店(秋田文庫)
初めて「恐怖新聞」に触れたのは確か、僕が中学1年生の時だ。
といっても原作を読んだわけではない。タイピングソフト「恐怖タイピング新聞」をプレイしたのだ。家族は誰一人として恐怖新聞を読んだことがないのにもかかわらず、なぜかそれが家にあった。当時、ブラインドタッチに猛烈な憧れがあった僕にとってこのソフトとの出会いはまさに渡りに船であった。学校から帰ると、すぐにデスクトップパソコンのスイッチを入れる。windowsXPが立ち上がり、どこかの草原の壁紙が現れる。あの草原は実際に存在するらしい。デスクトップに貼られた「恐怖タイピング新聞」のまがまがしいショートカットをダブルクリックし、それを起動する。
このゲームは恐怖新聞のいくつかに分かれたテーマである「頁」ごとにステージ分けされている。最初はキーポジションの確認をするステージ、次は実際に指定された(1字の)文字を打っていくステージ、次は短文、次は長文…といったようにステージをクリアするごとにタイピングの難易度は上がっていく。僕は日夜このゲームに没頭することによって、ブラインドタッチができるようになった。そして、学校のパソコンの授業で僕はヒーローになれたのだ。
タイピングソフトの件はこれくらいにして「恐怖新聞」を読んだのは大学生になってからと記憶している。たまたまブックオフで探索をしていたときに、文庫版「恐怖新聞」(全5巻)を見つけたのである。タイピングソフトをプレイしたことにより、恐怖新聞の大枠のストーリーは何となく理解していたが、原作を読んでいないとハッとなり、購入した。初出が1973年ということもあり、どうしても古さは感じたが、著者の怪奇に対して貪欲に調査し、漫画に昇華させていく様に驚いた。「あとがき」においても様々な著名人が言っているが「恐怖新聞」はありえない話の中に、ひょっとしたらこれは本当の話なのかもしれない、と読者に思わせるようなリアルさが介在している。「恐怖新聞」が我が国における1970年代オカルトブームのさきがけとなったことはほぼ間違いないだろう。それは著者のたゆまぬ心霊研究の賜物であると感じる。
あらすじ
しんぶ~ん!!
つのだじろう [1996] 『恐怖新聞1(序章 真夜中に奇怪な新聞が来た)』 p.13
石堂中学校に通う鬼形礼。ある日彼の自宅に恐怖新聞が届く。その新聞を読むと寿命が100日縮むらしい。そして時を同じくして彼にポルターガイストが憑りつく。新聞を読まなければ、ポルターガイストにひどい目に遭わされる為、鬼形は不本意ながら恐怖新聞を毎日読み込んでいく。その内容はある種の予言文であり、鬼形の周りで起きる様々な怪奇現象について記述されている。彼は恐怖新聞を通して、怪奇の世界へと迷い込んでいく。
書評
逃げられない恐怖
恐ろしいことです…
つのだじろう [1996] 『恐怖新聞1(序章 真夜中に奇怪な新聞が来た)』 p.78
ぼくにとりついた憑依霊は僕の命を百日ずつへらしながら…
むりやり「恐怖新聞」をぼくに読ませるつもりなのです!
恐怖新聞を支える根本的要素として、鬼形礼とポルターガイストとの関係が挙げられる。ある日突然どこにでもいる中学生の男の子にポルターガイストが憑りつく。その理由は鬼形が「幽霊を信じていなかったから」である。この時点で当時の読者はドキッとしたはずである。そして鬼形はポルターガイストが毎日届ける恐怖新聞を無理やり読まされるわけであるが、ここにも素晴らしいからくりがある。それは、恐怖新聞が短編オムニバスという形式をとる上で毎回新聞に書かれた記事をベースに話が進む点である。新聞の内容は大きく二つであり、起きた怪異の説明と起きる怪異の説明である。つまり、怪異発生のたびに怪異(ポルターガイスト)の視点で説明が入り、かつ物語にちりばめられた怪奇な情報によって、読者自身は演繹的に鬼形の経験を追体験するわけである。その一連の流れを踏むことで、読者は物語にリアルさを感じ、その感覚は濃い恐怖となっていつまでも残り続けるのである。
また、新聞を読まなければ良いと思われるかもしれないが、無理なのである。新聞が届くと、不思議と記事に目が吸い寄せられてしまうのである。では、新聞が届かないように戸締りをすればよいのではと思うが、それも無理だ。恐怖新聞は雨戸をぶちやぶって部屋に入ってくるのである。こういったありえない内容も、メタ的スパイスになり、読者を楽しませる。
頁
それでは白の頁へご案内いたしましょう
つのだじろう [1996] 『恐怖新聞1(序章 真夜中に奇怪な新聞が来た)』
「恐怖新聞」は全27話で構成され、その1話1話が白、赤、青、黒、紫の頁という5種類の要素に分類されている。それぞれの「頁」は下記である。本稿ではこれらのジャンルごとに書評を記述しようと思う。2
白の頁(霊の世界)
憑依霊や、ドッペルゲンガーなどの所謂心霊学における「霊」に関係する話。
リシェがエクトプラズムを提唱してから百と三十年ほどが経過したが、あの白いモフモフべたべたした物体はどこにいったのだろうか。「白の頁」の挿絵にエヴァのエクトプラズムを使用したのはセンスが良いと思ってしまう。「ねないこだれだ」のお化けや、怪談レストランのお化けギャルソンを想起するが、その原型はエクトプラズムであることを改めて思い知らされた。
一度でいいから、幽体離脱を経験してみたいものである。
赤の頁(怪奇の世界)
今で言う「怪談」や「都市伝説」などに分類される話。
かなり好きな頁である。「名投手怪死」などの中長編から、「笑う骸骨」といった短編までバランスよく取り揃えられている。
少々本作における「白の頁」と「赤の頁」の境界が曖昧に感じる。赤の頁に一ジャンルとして包含されるのが白の頁であり、白の頁に分類されている話にはほぼ異論がないが、赤の頁に分類されている話で「ふとん」などは本来白の頁に分類されそうではある。現象の原因を「怪全般」とするか「霊」とするかが二者に分かつ基準ではありそうだが、その判断はなかなかに難しいものではある。例えば「名投手怪死」において、選手たちを怪死に追い込んだのは「呪い」である為、本作を「赤の頁」に分類したと思われるが、元を辿れば「呪い」は人の情念であり、見方を変えれば「生霊」とも取れるため「白の頁」に分類される可能性もあるだろう。
子供のころ、必死に読み漁っていた「学校の怪談」シリーズ。その中の話を恐怖新聞的に分類するならば、ほとんどが赤の頁に分類されるのではなかろうか。「口裂け女」や「トイレの花子さん」「人面犬」、走る「骸骨」や「二宮金次郎」など、名前を与えられた怪異はすべて原因が不明のように思えるからだ。「トイレの花子さん」は戦時中にボットン便所で死んだ女の子の霊である、と言われたところで、その女の子と、「トイレの花子さん」は明らかに別概念である。口承の途次で様々な要素が追加削除されることにより、その女の子は全く別の「怪異」となってしまうところに、怪談の面白さはあるのだと思う。つまり「トイレの花子さん」事象の原因はその女の子になく、口承過程の人間達の意思にあるというわけである。そういったあいまいさや、人間の創作性が垣間見える点において、僕は怪談が好きなのである。
青の頁(宇宙の世界)
UFOやUMAに関係する話。
いきなりこんなことを書くのもどうかと思うが正直な話をすると、僕はあまりUFOに興味がない(詳しくない)為、あまり楽しめなかった(笑)。思えば、僕は幼いころから宇宙人と言うモノに関して、何かこうピンとこなかったからである。
「地球外生命体(宇宙人)は存在しないことはない」これが僕の宇宙人に関する結論である。それはこの広大すぎる宇宙の隅々まで調査していないことが根拠である、というある種凡庸な意見を標榜し、それで僕の中で話は終わりなのである。怪奇と言うモノを論ずるフィールドが地球から離れてしまうと、とたんに興味も離れてしまうのである。そのため、ネッシーなどのUMAはまた別である。ツチノコやビックフットは存在してほしいと今でも願っていたりする。
「円盤着陸」ではアメリカパスカグーラの宇宙人事件を題材としており、所謂ゲームのマザーのスターマンそっくりな銀色の宇宙人が登場する。比較的、青の頁はほかの頁よりも(UFOに関する)細かい情報がたくさん載っている為、作者がUFO研究にかなり力をいれていることが分かる。きっと当時の子供たちは望遠鏡を買ってもらって夜空に思いを馳せたに違いない。
黒の頁(伝説の世界)
四谷怪談やピラミッドの呪いなど、伝説にまつわる話。
赤の頁のうち、歴史性や伝承性が高いとここに分類されるイメージである。「黄金百枚」や「ファラオの呪い」からみても、当時世間を騒がせていた内容が散見される。
中でも覚えていたのは「背中がこわい」である。僕の実家の近くにあるお寺の脇の道に「おんぶお化け」なるものが現れるという噂があったからである。しかも祖母はその脇道で実際におんぶお化けにおんぶをされたことがあるらしい。その後、おんぶお化けの伝承を調べると新潟県の「おばりよん」という妖怪や、広島県の「おいがかり」という妖怪ががヒットした。いずれも「おんぶ」をしてくる妖怪である。確かに重い荷物を背負って、外を歩いていると、急にその重みが増すことは多々あることかもしれない。「疲労」という重みが背中を襲うわけである。
また、例のタイピングゲームにおいてもこの「背中がこわい」はステージとして収録されていて、かなりの長文を入力しなければならないため、最初はかなり苦戦したということで、僕の記憶に深く残っている。
紫の頁(悪魔の世界)
悪魔に関連する話。
全1話、「悪魔のカード」のみである。恐怖新聞中盤の核たる中長編で、悪魔憑きの要素だけでなくタロットカード、鬼形に憑いているポルターガイストと悪魔アグニとの戦闘も描かれる。
少し論点がずれるかもしれないが、小さいころこの手の悪魔祓いや除霊によって霊能者が憑き物を祓う、という内容の番組がよく民放で放映していた。僕はそれを見るたびに、霊や悪魔といったものが語る言語はきっと全世界共通であるのだなと思ったものだ。本作のアグニも出身はスペインであると考えられるが、東や鬼形に憑りついた時に流暢な日本語を話していることからも彼等は全世界共通の言語を会得しているに違いない。これは別に作品や除霊を馬鹿にして言っているわけではない。きっと霊や悪魔といった超自然的存在における言語という概念には、我々人間が区別するような言語体系が存在しないということの現れなのかもしれない。
悪魔は不浄のものを好むという点も面白い。本作で登場する悪魔アイニもゴキブリを好み、食し、町中のゴキブリを呼び寄せることができる。ゴキブリ嫌いの僕にとっては狂気の能力だ。ゴキブリご飯の描写はとてもリアルで寒気が襲った。また、楳図かずおの「洗礼」よりさくらが和代に与えたゴキブリ粥を思い出した。その行為はヴィジュアルが恐ろしいだけでなく、「悪魔」を示唆できる点でとても有効であったのかもしれない。
物語の帰結
あの「恐怖新聞」を運んでくる恐ろしい霊が払えるのなら僕はどんなことでもがまんする!
つのだじろう [1996] 『恐怖新聞5(第二十六話 他人の顔)』 p.78
様々な怪異を経験する鬼形、その過程でポルターガイストを除霊するチャンスがきたり、ポルターガイストと少し仲良くなったりするわけであるが、やはり怪異は怪異、結局二者は相容れることはなく、鬼形はポルターガイストの除霊を試みる。そんな最終回にて、結論を言うと除霊は失敗し鬼形は死ぬわけだが、この部分に「恐怖新聞」のシビアさを感じる。鬼形は主人公であり、かつ中学生の子供で「恐怖新聞」は少年漫画に掲載されている作品である。そんなメタ的要素を鑑みると、ポルターガイストも祓えてハッピーエンドになりそうなものであるが、そこをそうさせず最後の最後で鬼形を殺してしまうつのだじろうに感服した。この物語の主人公は「鬼形礼」ではなく、我々「読者」だったのかもしれない。それは、この物語が鬼形礼が恐怖新聞を配るシーンで幕を閉じる点からも明白である。鬼形礼は死ななければならなかったのである。そして、今度は読者自らが「恐怖新聞」の餌食になることを示唆して物語は終わり、読者は震えあがるというわけである。
本当に、つのだじろうは怖い漫画家である。
まとめ
僕は意外にも「幽霊」はいないと思ってる側の人間である。そんな僕がホラーが好きなのは人間が創作した怖い話に興じるのが好きだからである。その結果「怖い」と感じることが何とも快感なのである。「幽霊」は信じないが、「幽霊」の話は好きなのである。
幽霊が見える人とそうでない人における違いの一つに、知覚の可否というものがある。それは例えば、人間が常に見ている色、自己の見えている色の見え方は他人と共有することは不可能である。それは色の知覚は主観的要素が強いためである。このことから、人間の知覚する色には個体差があるということが言える。ある人には見えて、ある人には見えない色が存在するそうだ。そしてそれは色だけではなく「幽霊」も一緒なのではないかという説である。このことから、厳密にいえば、僕は幽霊をいないと思っているのではなくて、いることを知覚できないのである。そしてこれは「見えない(・見たことない)ものは信じない」ことと同義のようでそうではない。僕はできるものなら幽霊を知覚したいのである。そう願い続けて、僕もだいぶ大人になってしまった。だから幽霊は信じようがないのである。
今夜あたり、僕の家に恐怖新聞が届いてしまいそうな気がして、わなわなと震えた。
- 1973年から1975年まで週刊少年チャンピオンにて連載される。 ↩︎
- 以下各頁ごとにタイトルのみ記載する。
白の頁(霊の世界)
「序章 真夜中に奇怪な新聞が来た」
「第三話 自分と自分」
「第七話 百物語」
「第九話 うらみの火が燃える」
「第十一話 不幸の手紙」
「第十八話 ピアノ」
「第二十三話 交霊会」
「第二十五話 交霊会(竹之市再生続き)」
「第二十六話 他人の顔」
赤の頁(怪奇の世界)
「第一話 誰かが噛む」
「第六話 山小屋の怪」
「第十三話 笑う骸骨」
「第十四話 名投手怪死」
「第十七話 奇妙な妹」
「第十九話 ドラフトの星」
「第二十話 ふとん」
「第二十一話 風呂」
「第二十二話 自転車」
青の頁(宇宙の世界)
「第二話 空に光る謎」
「第八話 北極点の謎」
「第十五話 円盤着陸」
黒の頁(伝説の世界)
「第四話 真説四谷怪談」
「第五話 ファラオの呪い」
「第十話 黄金百枚」
「第十六話 背中がこわい」
「第二十四話 竹之市再生」
紫の頁(悪魔の世界)
「第十二話 悪魔のカード」 ↩︎
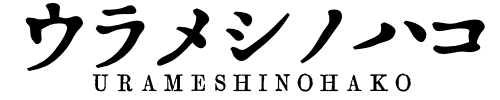


コメント