怪談レストラン⑤ 妖怪レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集 松谷みよ子
絵 たかいよしかず
1996年10月20日 第1刷発行
童心社
怪談レストランシリーズ全50巻あるうちの第5巻目、妖怪レストラン。
表紙には緑の河童が描かれている。右手には何やら魚の兜焼きのようなほかほか料理。半笑いの顔でこちらを見ている。たくさんいる妖怪の中から河童をチョイスした怪談レストラン編集委員会の皆さまのセンスに感謝である。僕は幼少期河童に会いたくて、近所の池にきゅうりを持ってでかけた思い出がある。もちろん河童には会えず、代わりに蚊にこれでもかと言うほど刺されて帰ってきたわけだが…
彼の名はカパカパ。
本作をみるに彼はオーナーでもコックでもなさそうである。ただ妖怪レストランにさまよう数多の妖怪のうちの一体として選出された感じがある。いっちょ前に蝶ネクタイをつけているのもかわいらしい。
あらすじ
ようこそ 妖怪レストランへ!
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.3
今回の舞台は山の古ぼけたお寺である。様々な妖怪が集うそこは彼らが経営するレストランだ。お客さんは人間なのか、妖怪なのか、付喪神なのか。とにかく騒がしそうである。オーナーは黒鬼、ボーイは一つ目小僧が担当しているらしい。また、カパカパが変装してるであろう男も登場しており、彼の役職はなんなのだろうか。
読者はゲストとなり、当レストランでお料理(お話)をいただくのである。
作品は全15話のオムニバス形式で描かれ、内3話は妖怪レストランに関する話、内12話は広義のホラーに関する話で構成されている。「妖怪」に関する話が多めの印象。「人面犬」「口裂け女」と現代の怪異の代表のような存在も登場する。p20-21 レストランのメニューを模した目次が非常に面白い。
メニュー
最初のおはなし 妖怪レストランのおいたち (松谷みよ子)
なまあたたかい風がふいていました。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.5
文頭の「なまあたたかい風」と言う表現がこのレストランにぴったりであることは妖怪好きの皆さまならすぐに気づくこと間違いなしである。廃墟となっていたお寺に集う妖怪たちが、レストランを開業するなんて可愛い話である。本尊は塗仏で、きっと裏手には墓場が広がり、テラス席になっているに違いない。人魂が場を明るく照らし、人面犬が走り回り、河童と口裂け女が夕餉を囲んでいるのかもしれない。
おきもののおはなし カッパのつぼ (松谷みよ子)
ふしぎなつぼなり。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.15
心が汚いものが手を突っ込むとその手を締め付けられるという壺。イタリアの真実の口に近しいものがあるが、手を嚙みちぎられることはないため、こちらの壺の方が優しいと言える。こういった所謂良い人が得をして悪い人が痛い目を見るというのは、妖怪談話の中でよくある要素だと感じる。
優しいおじいさんが家で大事に使っていた物をいじわるおばあさんが捨ててたあとで、その物が付喪神となり、おじいさんを妖怪レストランへ誘い、彼が河童の壺に手を入れて金を手に入れる情景を妄想してしまう。もちろんその話をおじいさんからきいたおばあさんが後日妖怪レストランを訪れ、河童の壺に手を入れても、結果は言わずもがなである。
人面犬 (望月新三郎)
なんだよ、ほっといてくれ
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.23
「ほっといてくれ」と言うセリフは本当に有名である。僕が子供の頃はなぜ人面犬はほっといてくれ、と言うのか今いちピンとこなかったのを覚えている。きっとそれは、中年のおじさんの心境と野良犬の心境を混ぜたことで生まれたセリフであると言える。休日家で寝転がってると奥さんと娘に邪魔と言われる中年、残飯をむしゃむしゃ食べる野良犬、この二つを足して二で割った結果、「ほっといてくれ」というセリフに至ったと考えられる。
また、人面犬にはキメラ説というものがある。そしてそれを生み出したのは筑波大学のある研究室であると本作でも明示されているがその理由については不明である。いずれ調べたい点ではある。
くちさけ女 (常光徹)
ねえ、あたし美人?
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.28
口裂け女に関する情報が記載されている。僕の実家の近くの山林で当時口裂け女が出没した騒がれたという事を母から聞いたことがある。が、それは何もこの地域に限られた話ではなく、1970年代後半当時はきっと全国的にこのような噂でもちきりであったのだろう。それだけ「口裂け女」は当時の子供たちの間で恐れられていたのだろう。
手のおばけ (馬場英子)
かまどからは、「ウウー、アウー」と、もがきくるしむ声がいつまでもきこえていた。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.42
「手」というシンプルな妖怪であるが、その持ち主はだれであろうか。ラジコンのように自由に操作できる墓場鬼太郎の「手」を思い出したが、本作の手もその持ち主が操作をしているのだろうか。しかし、「泰山」のまじないのあと、熊手が現れたという事はそうでない可能性が高いと言える。きっとこれは付喪神の一種だったのではなかろうか。
金曜日の行列 (剣持弘子)
ねこをもってたのは、あんたにとっちゃ、いいことだったよ。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.50
黒装束を纏った人間のお祈りの行列とは不気味なものである。彼らは魔女か、悪魔だったのだろうか。
猫というのは不思議な力をもっていると言われる。本作では魔除けの意味を果たしたが、日本では遺体の近くに猫を寄せ付けてはならなかったり、夜道で黒猫が前を横切ると不吉であったりと、良くない意味も彼らは持ち合わせている。そういった不可思議なところが、彼らの魅力であったりするわけで、まぁ猫好きの僕にとってはそんなことはどちらでもよかったりするのだが。
吸血鬼に恋したむすめ (八百板洋子)
ろうのように、まっ白い顔をして、うっすらと、ほほえみをうかべて。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.59
恋の恐ろしさを描いている作品。相手が吸血鬼と分かっていながら、逢瀬をやめられなかった娘は最終的に死んでしまう。本作は説話的側面も有しているのではなかろうか。中世の身分違いの恋、叶わぬ恋、実らぬ恋、世間は許さないが恋する二人はたとえ命を投げうってまでも、その恋を成就させたいと願っていたという事案が多かったことを示唆している作品であると感じた。
ホタルの夜のオートバイ (宮川ひろ)
あっ、吾郎さんだ
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.69
哀しくも、吾郎さんをホタルの光で表した絵は強烈で美しい。村人みんなの力でホタルを取り戻した背景を考えると何とも感慨深い。僕の実家の目前は昔、一面の田園風景で、夏になるとホタルが飛んでいた。手の中で煌々と光るあの黄緑の光を僕は忘れないであろう。今は国道が開通し、いなくなってしまったが…
つぎはおまえだ (沖井千代子)
おみごと、そのとおり。グハハハハ。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.76
有名な怪談。何者かが猟師を食べた後、何者かは誰に食われるのだろうか。
常に命のやり取りの中で生きている猟師だからこそ気づけたに違いない。
首つらせタヌキ (水谷章三)
ばっかやろうっ。なにがタヌキだ、なにがたたりだ。いいから、おれにまかせろっ
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.82
タイトルが怖い。思えば、人を殺す霊よりも人を自ら殺させる霊の方がその霊力は高そうである。これはタヌキというある一種の動物霊の霊力の強さを示唆しているのであろう。タヌキはよくキツネと並べて表現されることが多く、キツネに比べるとどこかおっとりとしてどんくささが強調されることが多いが本作のタヌキは非常に怖い。
セミの王さま (あまんきみこ)
その兄は高校のとき、バイクの事故で死にました。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.97
兄はセミの王になったのだろうか。いまいち作中の要素の関連性が読みにくい作品であるが、兄が高校で死んだことをきっかけとして彼の呪いが解けたことで妹が幼少期のエピソードを語れるようになったのであろう。つまりこの兄弟は兄が死ぬまでこのできごとを忘れていたと言える。それは非常に怖いことである。
僕はセミは昔から怖かったので捕まえたことはないので、この呪いにはかかっていないということで一安心である。
魂のつぼ (杉本栄子)
ヨーゼフだ。
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.103
湖の主を怒らせて魂がとらわれてしまった友人を助ける話。友人の魂が入った壺をひっくり返すが、この時点で友人は死んでしまい、湖の主が怒ってハンスも死んでしまうのだろうなという僕の予測は見事に外れた。本当に、怪異の基準は人間のそれとは相いれないのであろう。
わたしをかえして! (岡野久美子)
あんたの出番は、もうないよ
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.115
人面瘡の話ではあるが、何ともハッピーエンドである。強い意志と行動がいかに大事であるかが描かれている。そもそも、怪異とは人の心の弱みに付け込んでくるということを改めて認識した。
僕は幼少期人面瘡はできたことはないが、かさぶたをよくつくる子供であった。かさぶたができるとそれをはがすのが何よりの楽しみであり、僕の身体にできたかさぶたは一日と生きられない運命を背負うのであった。
おかげで、今僕の身体は消えない、古傷だらけである。
デザート カタリン (高津美保子)
カタリーン、カタリーン
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.124
典型的な人間が怪異に仕返しをされる話であるが、食べてしまったケーキの代わりに馬糞を入れるカタリンは鬼畜である。
魔女がカタリンを追い詰める様は「メリーさんの電話」を思わせる。徐々に迫る怪奇として描かれている。
最後のおはなし あるく人形 (松谷みよ子)
うれしくてあるくだか
怪談レストラン編集委員会 [1996]『妖怪レストラン(怪談レストラン)』p.134
かなしくてあるくだか
おからこ からこ
おからこ からこ
「わたし」と人形が対面するシーンは印象的で美しい。人形には生きてる人間の様々な想いが宿っていることが分かる。きっと、そこはあの世でもこの世でもない場所であったのだろう。
まとめ
妖怪を意識したのはいつからだろう。
幼い時に叔母に教えてもらって見始めた「ゲゲゲの鬼太郎4期」がそのきっかけとなったのは間違いない。その頃は幽霊や妖怪の違いなぞ意識することはなく、ただただ異形のモノとして彼らを認識していた。だが、そんな当時の僕でも両者を区別するある基準があったのだ。それは「怖い」か「怖くないか」である。ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪たちはみんな魅力的で怖いというより、かわいいものであった。仔細な定義や沿革は無視して、妖怪とはそういうものであると今になっても思う。
僕が妖怪の中で特に好きなのは、河童である。昔、父の書斎にあった「河童の涙」がそのきっかけであった。小さい瓶にキラキラしたガラスやビー玉が入っていて、綺麗であった。それは人間が環境を汚し、住処を奪われた河童の流した涙が具現化したものであると父に教わったときに、河童はなんて綺麗な涙をながすのだ、と子供ながらに感動したのを覚えている。それが本当に河童の流した涙であると信じて疑わず、きゅうりを握りしめ、近所の池に河童に会いにいったのは良い思い出である。
人間が捨てたゴミという負の要素が綺麗な瓶に入れられて雑貨になってしまうのは皮肉であるが、最大の皮肉はそれがとても「綺麗」であることである。
近々、岩手の遠野へ行ってみたいものである。
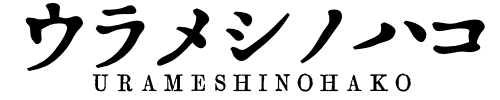


コメント