ギャシュリークラムのちびっ子たち
エドワード・ゴーリー
柴田元幸 訳
2000年10月25日 初版発行1
河出書房新社
エドワード・ゴーリーを知ったのは大学在学中の時であった。
当時、絵本でも怖いものを集めていた僕は、本作「ギャシュリークラムのちびっ子たち」と出会ったのである。たしかジュンク堂にて彼の特設コーナーがあったと記憶している。当初は、次々と死んでいく子供たちに何か意味や、原因があるものかと思った。つまり教育的側面を持たせ、何らかの戒めの物語であると。しかしそんなことはなかった。本作はただ、無意味に、淡々と子供が死んでいくだけの話であった。したがって子供一人一人の死に意味はなく、ただその最期を見させられるのである。これは子供の為の絵本でなく、大人の為の絵本なのだ。
あらすじ
A is for Amy who fell down the stairs
Edward Gorey(エドワード・ゴーリー) [2000] 『The Gashlycrumb Tinies(ギャシュリークラムのちびっ子たち)』 p.4
Aはエイミー かいだんおちた2
A-Zを名前の頭文字にもつ26人の子供たちがただ死ぬ物語。もやはこれは物語でなく、事実の羅列である。
書評
タイトルについて
タイトルの「Gashlycrumb」と調べもこのような単語はヒットせず、エドワード・ゴーリーの造語であると分かる。「Gashly」と「Crumb」を合わせた言葉であると考えられる。Gashlyはおぞましい、ぞっとする。Crumbはパンくず、かけら、のほかにスラングとして、使い捨てやとるに足らない存在という意味で使われるらしい。
直訳すると「悍ましく。くずのようなちびっ子たち」といったところであろうか。不思議なのは、子供たち自体が恐ろしく、取るに足らないような存在であるという表現がされていることである。これは誤訳であろうか。彼らの死にざまは確かに恐ろしいが、それよりもその身に起きた不幸の方が問題であろう。タイトルが「哀れな子供たち」であればまだわかるが「悍ましい子供たち」となっていることの違和感はじわじわと恐怖をかきたてる。
そしてこの作品の「or, After the Outing(または遠足のあとで)」という副題も興味深い。「遠足に行ったのあとに死ぬ」ということだろうか。いずれにしても「outing」という楽しい単語と、「Gashlycrumb」という単語は似ても似つかない。所謂ギャップを狙ったのであろうか。
意義
なぜ子供たちは死んでいくのだろうか。作品を読んでわかるのは、彼らは「殺された」わけではないということである。中にはごろつきにやられたり、喧嘩の巻き添いを喰らって死に至る者もいるが、皆がそういうわけではない。窒息死したり、溺死したりする者もいれば、なぜこんなことに、とその死の原因が分からない者もいる。ただ一つ言えるのは「ちびっ子」たちが、26人「死ぬ」ということだけである。
このことは、それらの「死」がある種超自然的な何かによって引き起こされているということを示唆する。表紙に描かれた死神のようなキャラクターもその根拠であるといえる。本来雨から身を守ってくれる傘を持っているのが印象的であるが、この場合この傘とは「死」という雨を引き寄せる象徴のようなものとして描かれている気がしてならない。
そもそも、その意味を考えること自体が愚策なのではなかろうか。この絵本を手に取った我々に残された道は、26の死を見ることだけなのだ。
痛そうな死に方ベスト3
全ての死に方を載せるわけにはいかないのでここでは三つ、僕が経験したくない、痛そうで苦しそうな死にざまをランキング形式で紹介して終わるとしよう。
第三位
L is for LEO who swallowed some tacks
Edward Gorey(エドワード・ゴーリー) [2000] 『The Gashlycrumb Tinies(ギャシュリークラムのちびっ子たち)』 p.26
Lはリーオ がびょうをごくり
壁に掛けられた巨大な絵画か、地図の前に座っている男の子。画鋲を飲み込んで死亡する。
僕は先日、サンマの骨をのどに詰まらせたがそれだけでも大騒ぎだった。画鋲となるとどんな感じなのだろうか。飲み込んだあと、あの鋭利な針がどこに刺さるかわからない恐怖。それは食道を通るとも限らない。気道を通って肺に達し、肺胞にぶっ刺さるかもしれない。考えただけでも、恐ろしい…
第二位
T is for TITUS who flew into bits
Edward Gorey(エドワード・ゴーリー) [2000] 『The Gashlycrumb Tinies(ギャシュリークラムのちびっ子たち)』 p.42
Tはタイタス どかん! こなみじん
男の子が何やら四角い包みを持ってたたずんでいる。
この文章、挿絵をみても「どかん、こなみじん」の意味がわからないのである。何かに「どかん」とされて粉みじんになることはわかるのだが、どうされて粉みじんになるかが不明なのである。何か重機のようなものに押しつぶされて粉みじんになるかもしれないし、爆破されて粉みじんになるかもしれない。何が起こるかわからないということは恐怖を助長させるものである。
第一位
X is for XERXES devoured by mice
Edward Gorey(エドワード・ゴーリー) [2000] 『The Gashlycrumb Tinies(ギャシュリークラムのちびっ子たち)』 p.50
Xはザークシーズ いたいいたいねずみの(歯)は
密室の隅に追いやられた男の子。無数のネズミが彼に迫っている。要は、生きながらにしてネズミの餌となってしまうのである。これが堂々の一位であった。きっと皮膚を喰い破られたくらいじゃ中々死なないであろう。自分の臓物をむしゃむしゃとネズミが食い荒らすのを見ている様は地獄に相違ない。ザークシーズは己に開けられた穴からネズミがちゅーちゅー顔を出す姿を見ながら死んでいくのである。
まとめ
本のデザインの話をすると、この絵本はとても小さい。縦*横約13cm*16cm程でかなりコンパクトだ。そのため本棚に背表紙を向けて差し込むのではなく、表紙をこちら側に向けて立てかけたりすると、おしゃれでインテリアとして良い。僕はこの本を友達の誕生日にプレゼントしたことがあるほどである。ちょうどいい感じに恰好がつくのでおすすめである笑
無意味に死んでいく子供たちを、この世界の無常と関連付けようともしたが、きっとそれはミスリードであるだろう。なぜならこの作品は「ただ26人の子供たちが死ぬ作品」であるのだから。
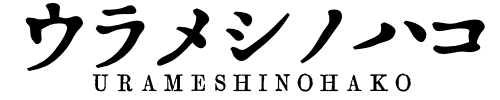


コメント