怪談レストラン⑨墓場レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集 松谷みよ子
絵 かとうくみこ
1998年2月25日 第1刷発行
童心社
怪談レストランシリーズ全50巻あるうちの第9巻目、墓場レストラン。
表紙には女の幽霊が描かれている。そしてその周りには水色と肌色の人魂が浮遊している。彼らは女の幽霊の髪の毛や着物の袖、彼女が持つお盆に載せられた「墓場(料理なのかこれ..)」を舐めたり齧ったりしている。人魂というのは存外雑食で、食いしん坊なのか。
彼女の名は幽霊ねえさん。
墓場レストランのオーナーである。白装束に青色の帯を締め、脚はなく、幽霊のそれを携えてふわふわと宙に浮いている。顔面は白塗りであるが真っ赤な口紅がアクセントになっていて、額には三角巾をまいている。まさに幽霊そのものの姿形を呈している。
以前「幽霊屋敷レストラン」の記事の冒頭でも書いたが、この「墓場レストラン」が、僕が人生で最初に出会った怪談レストランシリーズの一冊である。この本を父の書斎で見つけたのだがなぜかカバーがついていなかった。なので僕が怪談レストランシリーズ収集を始めた際に買い直した。当時まだ小さかった僕に取ってはなかなか難しい単語や文章だったが両親にその意味を聞きつつ読破したのはいい思い出である。

あらすじ
ようこそ フリートホーフレストランへ
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.2
日本語にいたしますと墓場レストランと申します
墓場レストランはビルの地下に存在する。そのことから、フランスのカタコンベを彷彿とさせる。日本において「墓場」と聞くと、灰色の墓石になになに家之墓と掘られている文字、献花、線香の紫煙が脳裏に浮かぶ。そしてその地面には骨壷が安置してある。そういった慣習などから、墓場レストランは地下に立地しているのだろう。
本作ではある一人の男が墓場レストランに足を運ぶ、ロビーにある穴の件は、涙ちょちょぎれる仕上がりとなっている。
読者はゲストとなり、当レストランでお料理(お話)をいただくのである。
作品は全15話のオムニバス形式で描かれ、内3話は墓場レストランに関する話、内12話は広義のホラーに関する話で構成されている。「墓場」に関する話が多めの印象。p4-5 レストランのメニューを模した目次が非常に面白い。
メニュー
最初のおはなし 墓場レストランのできたわけ (松谷みよ子)
その、墓場の上にたった、ビルなんです。
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.14
墓場レストランの料理は、ビルや周辺の人間だけでなく、昔戦死した者たちの魂にも振舞われる。思えば、今僕たちが暮らしている家の土地は、昔たくさんの人が死んだ場所であるかもしれない。そう考えると世界中どこでも「墓場」なのではなかろうか。amazarashiにそんな歌があったっけな。
あなのおはなし ロビーでふしぎなあな (松谷みよ子)
一枚、おうつしください。おかえりまでに現像しておきます
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.20
最終話「一枚の写真」に繋がる話。「墓場」である地面の下の下まで続いている穴は、さしづめ霊の通り道となっているのだろう。それにしてもこういう地面にあいた、そこの見えない穴には底知れない恐怖を感じるものだ。自分が落ちてしまったら、そう考えるだけでサブイボが止まらない。
かべにかざられた手 (杉本栄子)
汝の父母をうやまえ
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.24
汝の…命の…なり…一六…
彼が死んでまで暴力に訴えたのはなぜなのだろうか。冷たい墓穴で地獄の責苦を受けたのにもかかわらず、地面を突き破り天に突き上げられた拳はそれだけで異常なのが分かる。「暴力」の罪深さを描いているのだろう。テーブルの上に残された、空のワイングラスと、血のような赤ワインの滴は、一体何を表しているのか、不明であるが。彼が生きた時代のワインということが何か関係をもっているのだろうか。
どくろのスープ (岩倉千春)
おれの頭だ。もっていくな
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.34
墓をあばいて頭蓋骨を盗みスープを作るなんて、このおばさんは肝っ玉が据わっている。しかし牛の病の元凶や、人間のどくろスープがなぜ有効なのかについては判然としない。
墓守のむかし語り (岡野久美子)
なになに?「幽霊なんてしんじない」って?
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.50
墓守が墓にまつわる怖い話を2つ披露してくれる話で、オチはその話者である彼もまた幽霊であるというものだ。2つ目の話は死んで埋められたものが復讐を遂げる話で、幽霊となって犯人に近づき、彼を自らが眠る棺桶に引き摺り込むというなんとも怖い話である。閉所恐怖症の僕としては発狂を免れないだろう。
雨の夜の客 (岩崎京子)
うしろのシートをみると、ぐっしょりぬれていました。
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.58
タクシー運転手が雨が降る晩に、女の人を乗せるも、気がつくと彼女は消失し、後部座席がびっしょりと濡れているという有名な話。言わずもがなシートを濡らしている水分は「雨水」であるが、僕は幼い頃この話をきくと、女の人がお漏らしをしてしまったんだと思っていて、これは汚い話であると認識していた点については内緒である。
見たな (吉沢和夫)
そんなからだで、お国のために役立つ人間になれるとおもうのか。からだがよわいのは、お国をおもう精神がたるんでいるからだ
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.59
この手の話は非常に多くの類型をもつが、今回は虚弱体質の男の子が墓を暴いて骨を齧る話だ。彼はいつのまにか死んでしまっていて知らぬ間に「化け物」と入れ替わっていたのか。
その正体は依然として謎のままである。
墓よせ (水谷章三)
わたしの村では、むかしから、仏さまには、かならずあたたかいごはんをあげることになっています。どうしてかっていうと、仏さまは、ごはんの湯気をすうからなんなそうです。
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.69
うちの実家でも仏壇には毎朝炊き立てのご飯と一番最初に淹れたお茶をお供えしていた。当時、なるほどそれらの湯気を、仏さんが吸うのかと納得したものである。
墓地にでた魔物 (常光徹)
おばさん!せなかがまっ赤だよ。赤ちゃんが…
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.82
「墓場レストラン」で一番怖い話である。かつ僕はこの話が一番好きだ。女はたった千円と引き換えに大切な赤ん坊を自らの手で殺してしまったのだ。後味の悪さは天下一品である。また、女はミルクを買うお金すらないことから貧乏であることはわかったし、親類に助けを乞うこともできず、自ら母乳を搾ることもできないほど衰弱、夫は放蕩三昧…などという妄想も捗る名作である。
ショキン ショキンと音がして (宮川ひろ)
ショキン ショキン
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.89
その不気味な音とは反対に意外に心あったまるできとなっている。母の霊は子供が心配で成仏できないのであろう。
きもだめし (小沢清子)
ふふっ、火葬場はね、もっとこっち
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.98
今の子は、肝試しをするのだろうか、僕が小さい頃、夏のお泊まりイベントの目玉といえば肝試しであった。山道や、お寺、お墓の脇道などを通って、ゴールに向かうのである。年長者の友達や大人がルートの至る所に隠れていて、僕らが通るとわ!と脅かしてくるのである。もはやそんなことしなくとも、夜の、今ほど明るくない田舎の道は、本当に怖かったものである。
花嫁衣装 (斎藤君子)
おかあさん、もうなかないで。おかあさんがなくと、わたしだってつらいの。
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.108
彼女はあの世で好きな人を見つけて幸せになれた、ということなのだろう。それにしても服をあの世に送る際の転送手段は、なかなか面白い。
霊のとおり道 (高津美保子)
きこえるか、死者たちがうれしそうにかたらうのが。みえるか、たのしそうにおどるのが
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.122
日本にも霊道の概念はあるが、そこを通る霊たちが、その付近の建造物を壊すというものは初耳である。これはドイツの話であるが、世界の幽霊譚は個性的で面白く、まだまだ僕の知らないことがたくさんあるのだなと感心する。
デザート おまえにひとつ、おれにひとつ (剣持弘子)
あとは、あの門のかげのふたつだけだな
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.131
オチがしっかりしていて落語にありそうな面白い話である。
ちなみにこの話の面白さを幼い頃の僕はいまいちよくわかっていなかった笑
最後のおはなし 一枚の写真 (松谷みよ子)
でも、花野の中で、すこしわらっているのは、たしかにかあさんでした。
怪談レストラン編集委員会 [1998]『墓場レストラン(怪談レストラン)』p.137
この男は墓場レストランからの予想外のプレゼントに感動したことだろう。きっと、行けてなかった実母の墓参りに行くことだろう。そして、前を向いて人生を歩んでいくことだろう。
どこかで聞こえたインチキだとという罵声も、それはそれで、人間らしくて良いものだ。
まとめ
死者の魂はお墓にはおらず、風となって残されたものを見守っているという歌が日本で流行ったのはもう今から20年ほど前であるという事実に、時の流れの早さを感じ、わなわなと震える。死者が墓場にいないなんてことは誰もがわかっていることである。しかしそれでも我々はお墓参りと称して年に何回かお墓を訪れ、死者を偲ぶのだ。「墓場」は生者と死者を結びつけてくれる一種の装置なのではなかろうか。また、遠方に散り散りとなった親族が一同に顔を揃え、死者の思い出話を語り合うという点においても、感慨深いものがある。墓場はネット墓場でOK!お線香はクリックであげるのが、楽だよね!と普段から思っている僕は野鄙な近代病に罹ってしまったのかもしれない。
今度お墓参りに行こうっと。
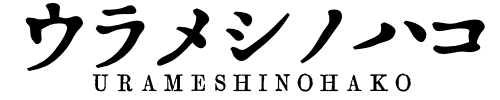


コメント