いるのいないの
京極夏彦 作
町田尚子 絵
東雅夫 編
2012年2月10日 第1刷発行
岩崎書店(怪談えほん)
木々が覆い重なってできたトンネルの中、公民館の地下のトイレなど、夜でもないのに「暗い」場所がある。日中の明るさとは対照的なその暗さを見つめていると、なにやら吸い込まれそうな錯覚に陥る。それは暗闇にいる「何か」が我々を狙っているからなのかもしれない。
作者である京極夏彦は言わずと知れた妖怪小説の生みの親であり、僕も「姑獲鳥の夏」を読んだ時は衝撃を受けたものだ。鈍器を想起させるその本の厚さもさることながら、怪談としての大量の妖怪豆知識と推理小説としてのトリックの融合、そして個性豊かな登場人物に圧倒されたのを覚えている。当時僕は中学生くらいで、自分のことを妖怪博士だと思っていたが、この人には勝てないと唖然としていたのが懐かしい。
今回は、そんな彼の絵本について書こうと思う。このシリーズは「怪談絵本」シリーズと呼ばれ、他にも様々な作者による作品が多々あるが、どれも最高である。お子様に怪談デビューをさせたいと思っている親御さんの方々はぜひこのシリーズから選定するのを心からお勧めします。そして中でも一番お勧めなのがこの「いるのいないの」なのです。
あらすじ
おばあさんの いえで くらすことになった。
京極夏彦 [2012] 『いるのいないの』 p.4
とても ふるい いえだ
「ぼく」はひょんなことから祖母の家で暮らすことになった。
その家は古い日本家屋で、天井がなく吹き抜けだ。居室からは屋根裏が丸見えで、暗闇の中で梁や垂木が存在感を放っている。「ぼく」は天井裏を見たくない。だってそこには何かがいるのだから。
書評
いるからね
京極夏彦 [2012] 『いるのいないの』 p.33
ある客体がいるかいないかについて判断するときの方法で一番メジャーなのは、それを「視る」ことである。そして、その「視る」に至る動機としては、客体の存在を認識しているかいないかという二点が挙げられる。前者と後者では「視る」という行為に対して必然、偶然と言った属性を帯びる点で違いが出てくる。
一方で「視る」以外にも、「嗅ぐ」「触る」「聞く」などの感覚によって客体を認識することもできる。こと怪談においては、怪異を視認する前に生臭いようなにおいを感じたり、何者かに身体を触られたり、うめき声のようなものを聞いたりと、彼等はまず主体の視覚以外の感覚を刺激したあとで、視覚に訴えてくるものである。また、最初から視覚を刺激する場合であっても、その「視る」という行為はほとんどは「偶然」という属性を帯びている。なぜなら、怪異がいる確信をもって「視る」場合はほとんどないと考えられるからである。
この作品は、「ぼく」が怪異の存在を確信してからの心理描写を巧みに描いている。本来であれば「ぼく」が天井裏に怪異を発見したシーンで物語は終わるはずであるが、その際、挿絵は「ぼく」のアップになっている。そこから「ぼく」とおばあさんのやりとりが続く。「天井裏を見なければいないと同じ」というおばあさんの論理に翻弄される「ぼく」が興味深い。どう論理が展開されようと、天井裏に「いる」ことは変わらない事実である。また、「ぼく」が天井裏を見ていない間、怪異は変わらず天井裏にいると誰が言えよう。気が付いたらやつはトイレに移動してるかもしれないし、「ぼく」の布団の中に移動してるかもしれない。そういった付随的な要素も相まって、怪異から目を背ける時間が長ければ長いほど、その怪異を発見した時の怖さは大きくなる。
「ぼく」が最初に怪異を認識した時点で、怪異の矛先が読者に向くため、結局おばあさんとのやり取りも何もかも、最後に我々を怖がらせるために京極夏彦が拵えた精緻を極めた陥穽であると言える。我々はそれに気づかず、怪異がいると分かっていながら最後のページを開き、びっくり仰天するのである。
まとめ
僕は幼少期、夕暮れ時の自宅の二階が怖かった。
日が落ちて雨戸が閉められると、二階は電気をつけないと真っ暗であった。二階に続く階段を一階から見上げると、その暗さがより際立った。親に頼まれて二階になにか物を取りに行く際はもうドキドキだった。階段を上がって電気をつけるまでの時間、その逆もしかり、暗闇に身を置くのがとても怖かった。
あれからずいぶん時間が経ったが、今でも夜中、布団-トイレの往復のため暗闇を歩いてるとき、誰かに話しかけられやしないかと、ひそかに、ひやひやしているものである。
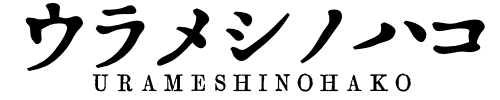


コメント