紗央里ちゃんの家
矢部嵩
2008年9月25日 初版発行1
角川書店(角川ホラー文庫)
いとこの家にはたくさん遊びに行った記憶がある。
中学生になる前までは週一でお互いの家を行ったり来たり、お泊り会なども頻繁に開かれていた。しかし、そのほとんどは、僕の家で行われた。いとこの家に泊まったことは、数えるくらいしかないと思う。
なぜなら、いとこの家には納戸があったからだ。
何と言うわけでもない、ただの納戸。
いつも雨戸を締め切っていて、真っ暗だった納戸。泊まった時、僕らが寝る和室から、廊下を挟んだところにある納戸。トイレは納戸の隣にあったため、夜中トイレに起きる際は、それが嫌でも視界の端にはいる。
何が、なぜ、怖いのかもわからない納戸。今ではいとこの家はリフォームされ、納戸は、ない。
本作を読んだら、そんな思い出がふつふつと湧き上がってきた。
本作は、作中を通してつねに「不自然さ」が漂っている。登場人物の誰一人にも感情移入を許さず、淡々と進行するこの作品はその存在自体がホラーなのかもしれない。グロ描写も多々あるが、主人公の発言通り、それ自体にホラーのスポットが当たっているわけではなく、登場人物のそれに対する「異常な反応」が怖さを引き立てている。
第13回日本ホラー小説大賞長編賞受賞作品。
あらすじ
そして最後の違いは、僕たちがその夏に訪れた時に、叔母さんの家に紗央里ちゃんがいなかったことだった。
矢部嵩 [2008] 『紗央里ちゃんの家』 p.5
夏休みの恒例行事である帰省。
「僕」は毎年、おばあちゃんや紗央里ちゃんに会えるのを楽しみにしていた。
しかし、おばあちゃんが亡くなってから初めての帰省。
叔母さんの家には、紗央里ちゃんがいなかった。
書評
何でお前だけそんなですんだの?おじいちゃんもおばあちゃんも、私だって家族なのに。お前だけ。お前が実は内側だったから?それともお前が外側だったから生きてるの?じゃあおばあちゃんもおじいちゃんも内側だったから、されたの?
矢部嵩 [2008] 『紗央里ちゃんの家』 p.156
まず、前提としてこの世界は「変」だ。
語り手である「僕」に始まり、父、叔母、姉、叔父、祖父、誰一人まともな人がいない。その属人的な「変さ」には何か理由があるはずだと穿って読んでいたが、そこに理由は存在しないし、それが語られることもない。また、頼みの綱である警察やテレビで放映されている内容もきちんと狂っていて、読者としては、何を信じてよいのかわからなくなる。
p.32に突然増える「ルビ」、文字の連続、唐突な三択、などの「活字のビジュアル」にも狂気を感じた。もちろんそこに意味などないのだろう。
そして、本作の主人公であり、語り手であり、被害者である「僕」に、まったく感情移入ができない。それは、彼自身が何に怯えているのか、何がしたいのか、なぜそれをしたいのか、まったくわからないからである。本作の内容を簡単に言うと「僕の死体探し」になるわけだが、その過程において、「僕」が感じるどきどきやわくわくは一切共有されず、グロテスクな事象とクレイジーな反応が淡々と描かれるのだ。
次に。作品のタイトルにもなっている「紗央里ちゃん」についてだ。
この物語の真の主人公は、彼女だったのではなかろうか。
物語の終盤で突然現れる彼女。車中にて彼女と「僕」の間でなされた会話が、この物語の意味を理解する上でとても重要なものであると感じた。それは「家族と親戚の距離感」ではなかろうか。彼女は、変わり果てたおばあちゃんを発見してしまった「僕」が、片耳を落とされるくらいで済んで殺されなかった理由として、「外の人間であるから」ということを指摘している。それは、誰もが感じたことのある様な、あの感覚をいびつにした果のセリフであると言える。一緒に住んでるおばあちゃんと、離れて暮らしているおばあちゃんの違い、もしくは一緒に住んでる叔母と、離れて暮らしている叔母の違いと言ったところだろうか。
「あの感覚」とは、一緒に住んでいるかいないかで、同じ家族や親戚であっても、例えば一年に一回しか会わないのであれば、その会っていない一年という期間に生じたお互いの変化に起因した、お互いの間に現れる壁である。その壁を基点として、こういった感覚をホラー味たっぷりに誇張した果に生まれたのが、本作であると僕は認識している。
まとめ
前置きに書いた「いとこの家」は、僕の実家と同じ市内にある。
僕にはもう一つ、宮城県に「いとこの家」がある。それこそ小学校の時は夏休みになると、帰省していた。一年に一回会えるいとことは、毎年纏っている雰囲気が違っていて、毎回打ち解けるまでに一日以上を要し、せっかく仲良くなったと思ったら、家に帰らなければならなかった。そして次に会えるのは、一年後か、もっと先か。
その距離感が、僕には不思議でならなかった。親戚だけど、家族だけど、10回会うためには10年かかってしまうこととか、会うたびに見た目も中身も変わってしまっていることとか、そういうことがとにかく、不思議だった。
今でこそたまに会えば、酒を飲む仲だが、僕が知っている彼らの今に至る軌跡は、ほんのわずかなのだ。
- 初出は「紗央里ちゃんの家」(角川書店) 1995年10月30日 初版発行 ↩︎
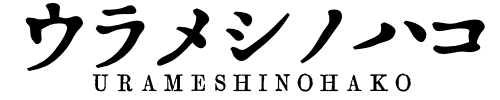


コメント