sink
いがらしみきお
1巻 2002年5月27日 初版発行1
2巻 2005年1月18日 初版発行
竹書房(BAMBOO COMICS)
いがらしみきおと言えば、「ぼのぼの」であろう。
僕はそう思っていた。僕は小さい時からぼのぼのの漫画を読んでいたし、アニメもビデオテープが壊れるほどよく見た。だがそんないがらしみきおがホラーを描いていると大学生の時に初めて知ったのだ。きっかけはまんが日本昔ばなしの「飯降山」を見た時だ。タイトルコールで演出と文芸が「いがらしみきお」となっていたのだ。そして本編を見て僕は驚愕した。なんて怖いんだ、と。
すぐに僕はいがらしみきおのホラー作品を調べ始めた。出てきたのはビックコミックスの「いがらしみきおモダンホラー傑作集 ガンジョリ」と本稿の「sink」であった。当時からホラーが大好きだった僕にとって、幼少期に大好きだった「ぼのぼの」の作者がホラーを描いていることは正に驚きであり、喜びであった。すぐにこれらの本を買いそろえ、読み耽った。今回は「sink」について書評を書こうと思う。
あらすじ
この前 街の中で交通事故があってそこに異様に首の長い女がいてな
いがらしみきお [2002] 『sink1』 p.28
「首の長い女」「腕の長い男」が現れたことをきっかけに、駿とその家族の日常をゆっくり蝕む非日常はやがて、家族の崩壊を招く。日常系ホラーの元祖といえる作品。
考察・書評
彼らはげんざと言う
人間が社会というものを作りはじめた大昔からそれに異を唱えつづけた血族だ
いがらしみきお [2005] 『sink2』 p.133
まず、本編を読む上で重要な要素である「げんざ」「よびしろ」「わけじいり」について簡単に記述する。
げんざ
大昔から人間が社会をつくることに反対し続けた血族。彼らの根本的な正体は不明。現代においても一般人の中に彼らの血を引く者が混じっている。
よびしろ
異様なもの。不幸。「げんざ」の血を引く者を目覚めさせる効力がある。「わけじいり」を作り出す。
わけじいり
所謂分岐点のようなもの。体験者はデジャヴュの様なものを知覚する。その後体験者は覚醒し「げんざ」となる。「よびしろ」によって作り出される。
日常を侵食する非日常
この漫画を布団に入りながら読んだとき、ページを捲るのを躊躇するくらいに怖かった。それは物語の節々に登場する物が「異様」だったからである。いがらしみきおはこの「異様」を作りだすのが本当にうまい。例えば、本編にはある朝突然電柱の高いところに針金で括り付けられた自転車が登場する。おそらく古今東西、こんな描写を作りだすのはいがらしみきお意外に僕は知らない。「電柱」「針金」「自転車」という個別に見たらなんともない物体が、ひょんなことから出会ってしまったが為に「恐怖」を生み出すのである。「sink」でも語られているが物事がバランスを崩すと「異様」が誕生し、それが人を不幸にするのである。これは本作に登場するホラーの概念の骨子であり、それだけでなく「いがらしみきおホラー」の根底に介在する概念のように思える。
ブログ冒頭に記載した「飯降山」の件だが、あれは僧侶の笑顔が何より怖いのである。これから人を喰らおうとする人間の表情は、恐ろしいものであると考えるのが普通であろう。その予想をいがらしみきおは裏切ってくる、そのことで我々が考えるバランスが崩れ(ギャップとも言うか?)、そののちに恐怖という波が襲ってくるのである。また「ぼのぼの」においても、シマリスくんの大姉ちゃんがたまに持っている土団子の謎を追う回で、ぼのぼのが色々と妄想を巡らすのだが、その内容の怖いこと怖いこと…
話が脱線したが、そういう崩れたバランスの中に恐怖を感じる要素があることは間違いないだろう。この「崩れたバランス」という表現は本当に素晴らしいと感じる。全てのホラー作品における「恐怖」要素はこの表現と密接にかかわっていると言えるのではないか。
本作に登場する「げんざ」とは何だろうか。物語では彼らは血族であり、人間かどうかは不明であるが、目を瞑ると姿を消すことができるため彼らが普通の人間ではないことは明白だ。「首の長い女」や「腕の長い男」「背の小さすぎる女」は皆それぞれ身体のバランスがおかしい。それは彼らが「げんざ」であることを示していると思われるが、なぜ「げんざ」はバランスがおかしいのだろうか。それは彼らが遥か昔より人間の社会性を否定してきたことに由来すると思われる。人間の社会というのはバランスが取れていると言えるがそれは逆説的に、バランスの悪いものが排他されている世界でもあるということだ。子供は保育園から大学まで、社会的に学ぶ。大人になると急に仕事をするようになり、社会はその一連の流れから少しでも抜けてしまった者を「特殊」であるとラベリングし、排他する。一度排他されると、もう一度元の流れに戻るのは難しい。いがらしみきおはそんな世界を皮肉って「げんざ」を創り出したのではなかろうか。つまり「げんざ」とは、バランスを崩して、人間社会から排他された人間たちのメタファーなのである。そしてここでいう「バランスを崩す」要因となるものが「よびしろ」である。
「よびしろ」と「わけじいり」は原因と結果の関係にある。要はよびしろが発生した結果、わけじいりに達し、その人間は「げんざ」になるのである。これを現実的に表現すると「ある事象が起きてから、人生が狂い、不幸になる」となるであろう。「sink」を読んで「怖い」と感じてしまった僕は、いがらしみきおの仕掛けた狡猾な陥穽にまんまとハマってしまったと言える。それは「げんざ」が意図せず不幸になってしまった人間たちを指しているからである。初めからそう描かれていれば、少しは「げんざ」の気持ちに寄り添い、駿の叫びに共感できただろう。狂っているのは、僕なのかもしれない。
最後に駿が母に伝えたことは何だったのであろう。父は最後までまともで、化け物になった息子を批判した。母は狂い、最後まで化け物の息子の味方であった。これは初めて「げんざ」と「人間」が分かり合えたということを表現していると思われる。母はげんざの新しい神にでもなったのだろうか。とすると、この物語はハッピーエンドであると、僕はそう考えることにした。
まとめ
sinkとは、名詞ではシンク(流し)、掃溜め、巣窟、動詞では沈む、落ち込むといった意味があるそうだ。掃溜め…この世界は掃溜めなのだ。この掃溜めの世界に集まるものをゴミと捉えて排他するか、雑多なものと捉えてわかり合おうとするか、この物語はそんな問題提起を孕んでいると考えるのは、幾分間違えであろうか。
僕も、決してレールの上を順調に走る人生をおくっていない。現在軌道修正中である。そんな僕はげんざになってしまうのだろうか。最近太ってきたし…よびしろが現れたらどうしよう…
- それぞれの初出を下記に記載する。
第1話 2001年2月1日
第2話 2001年3月1日
第3話 2001年4月1日
第4話 2001年5月1日
第5話 2001年6月15日
第6話 2001年7月17日
第7話 2001年8月31日
第8話 2001年10月9日
第9話 2001年12月25日
第10話 2002年2月9日
第11話 2002年3月26日
第12話 2002年5月31日
第13話 2002年7月19日
第14話 2002年9月18日
第15話 2002年11月14日
第16話 2003年2月20日
第17話 2003年4月16日
第18話 2003年7月17日
第19話 2003年12月25日
第20話 2004年10月12日 ↩︎
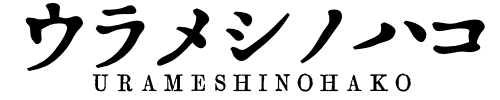
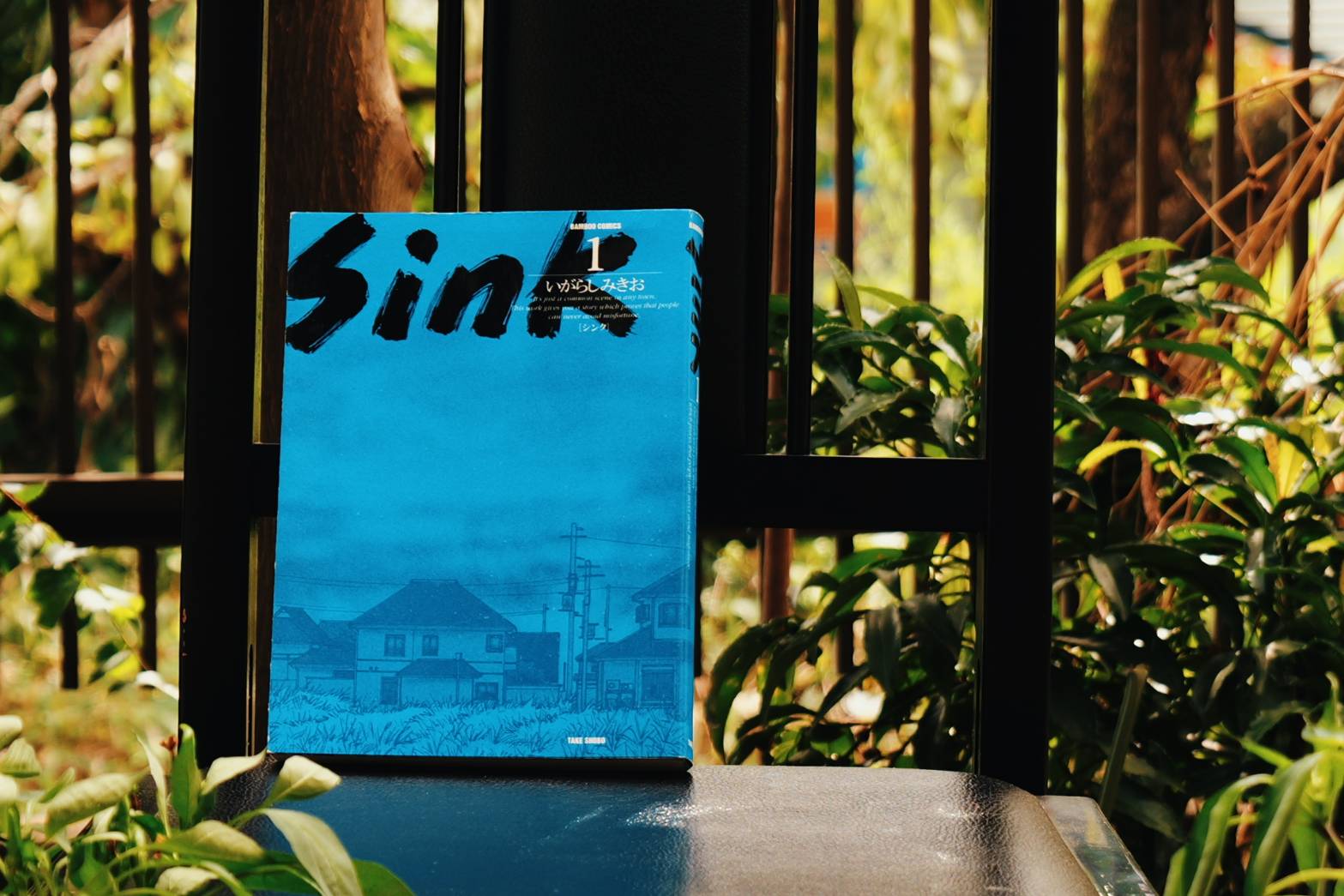

コメント